盛土地域(川路)の霧と逆転層について
今村理則*
The fog and the inversion layer in Kawaji, Iida city, Nagano
*Michinori Imamura
*〒 399-2566 長野県飯田市嶋99-2
飯田市川路は盛土事業で標高376.8mの高さに平された.その川路の霧が量質ともに薄くなったことを実感している.今回は、この川路の霧と逆転層との関係を調査することにした.夜の間、温度計を標高の異なる5ヶ所に設置し測定したデータと駒沢観測所のデータと対比するという方法で行った.その結果、風のない日には、標高380m~520mほどの間に少なくとも2層の逆転層があり、逆転層が形成されると霧が発生し始め、逆に逆転層の消失によって霧が発達することがわかった.なお、盛土地域は川路・竜丘・龍江の3地区にまたがる.
1.はじめに
秋になると川霧が出て10m先もわからないような道をよく登校した、という懐かしい思い出がある.しかし最近は霧が出る日が少なくなっている、あるいは出ても霧そのものが薄い.全国的な傾向なのか、それとも盛土地域の特徴なのかはわからない。特に盛土事業後は、その傾向が強いように思われる.2004年の秋には、視程が100m以下となるような”濃霧”は一度もなかった.
それでも川路の霧がどのように発生するのか、子どもの時に抱いた疑問に可能なかぎり迫ってみたい.
気層の高度による気温の変化を調べるには、気球を使う方法が最も理想的と思われる.しかし、経費が嵩むのでこれを断念して、かわりに川路周辺の山の傾斜地を利用することにした.
キーワード 盛土地域、霧、逆転層、放射冷却、風力、 雲の放射、気温、湿度
2.研究方法
時期:2004年の秋、よく晴れた風の静かな夜を選んでその午後6時ごろから翌朝の7時ころまで.
場所:川路の城山付近に5ヶ所と駒沢観測所の計6ヶ 所に温度計を置く.
①牧場の上の林(標高520m)
②城山の土取場頂上(標高480m)
③逆断層付近(標高450m)
④高松線交差点付近(標高420m)
⑤五郎島上(標高400m)
⑥駒沢気象観測所(標高380m)
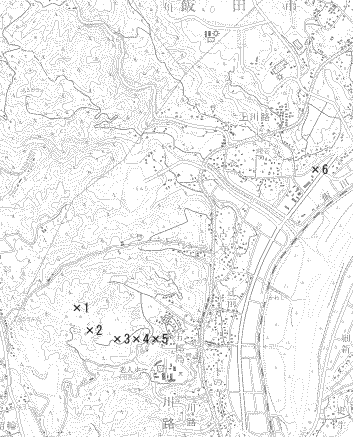
図1 温度計設置場所(1/2.5万図「時又」)
設置場所は×1~×6
観測地点⑥だけが1.5kmほど離れているが、標高が最も低い地点になるので比較のために入れた.
なお、各地点の標高は下記の高度計による。
観測機器:①高度計 Thommen classic,Switzerland
②温度計 Hobo ProSeries RH Temp
(米国Onset社)
温度計5個の誤差 ±0.2℃
3.逆転層とは
対流圏では一般に気温は高度とともに下がる。しかし、逆に高度とともに気温が上昇することもあり、この部分を逆転層という.逆転層には①接地逆転層②沈降逆転層③移流逆転層の3つがある.接地逆転層は、「夜間の放射冷却により、地表面付近の空気が冷えてできる逆転層である.冬季に雲がない夜、陸上で発生しやすい.霧(放射霧)も発生しやすい.日の出とともに逆転層も放射霧も消えはじめる.」(小倉1999)という.
このことから、川路に形成される逆転層は接地逆転層であることがわかる.
4.霧とは
霧は「直径数十μm以下の微小な水滴(または氷晶)が大気中に浮かんでいることが原因となって地表面付近で水平方向の視程が1km未満になる現象」(日本気象学会1998).
霧を発生原因によって分けると、「①水蒸気を含む空気塊の気温が下がって発生する霧で、移流霧・放射霧・混合霧・滑昇霧.②空気塊の水蒸気量が増えて発生する霧は、蒸発霧」(日本気象学会1998)となっているが、実際には、これらの原因のいくつかが複合して発生する場合が多いようだ.
盛土地域の霧は、①主として天竜川の川霧で川の水温が気温よりも高いことによって生ずる蒸発霧であり、②地面が放射冷却で冷えて放射霧も発生するだろうし、③逆転層による混合霧もありうる.川路の霧はこれらが重なって発生しているものと思われる.
5.観測データとその分析
(1)気温について
気温がある点まで下がらないと霧は発生しない.そのある点というのは、盛土地域の場合、天竜川の水温によって決まる.川の水温-気温≧5℃ の時に川霧が発生しているという報告がある(村井忍1992).
図2は逆転層を示すグラフから読み取ったもので、
霧が発生したと思われる気温と月日との関係を示す.
ただし、このデータには読み取りの作業が入るのでどうしても曖昧さが残る.
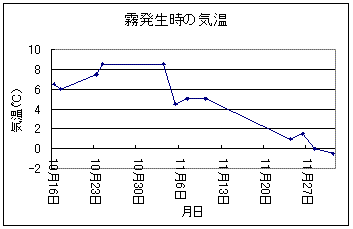
図2 霧が発生したときの気温
このグラフをみると、全般的に右下がりで、日を追って霧が発生する時の気温が下がっており、天竜川の水温も同じようなペースで下がっていることを裏付けている。なお気温が0℃以下になると、多くの場合に霧は霜にかわる.
なお、初めの10/16(6.5℃)、10/17(6.0℃)、10/23(7.5℃)、10/24(8.5℃)、11/3(8.5℃)と終わりの12/1(-0.5℃)には視程1km以内の霧は発生していないが、参考データのために加えた.
次に、夜の間の気温は、放射冷却が進むのでほぼ一様に下降する.図3に霧が発生した11/3と11/5の気温の変化を示す.データは駒澤気象観測所のもの.
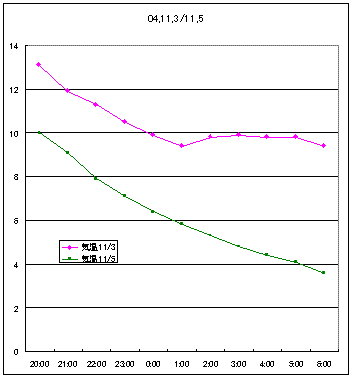
図3 一夜の気温の変化
気温が高い方の11/3の変化をみると、午前2時には気温が上昇している.
一般に、風のない静かな夜に途中で気温が上昇に転じるのは①雲が広がって、この雲から比較的長い波長の放射を受けるか、あるいは②霧が発生して水滴が生じたために、その潜熱が解放されるか、のどちらかである.あるいは①と②が重なる場合もありうる.
このグラフからはその上昇の原因をつきとめることはできないが、後に示す逆転層のグラフによって、②の霧の発生による昇温と考えることができる.
では、11/5の下のグラフには昇温の部分はないが、霧の発生はなかったのだろうか.メモによると、この日の朝の霧があって9時半ごろにあがるのが確認されている.この日は霧の発生が遅れて6時以降にずれこんだためと思われる.このことは逆転層のところでもう一度ふれる.
(2)湿度
調査を始める前には、湿度のデータは欠かせないと考えていた.しかし、データを分析してみると、相対湿度が100%でも霧ができているとは限らないし、また100%の地点があまりにも多すぎて、解釈についての決め手を欠くことが多い.
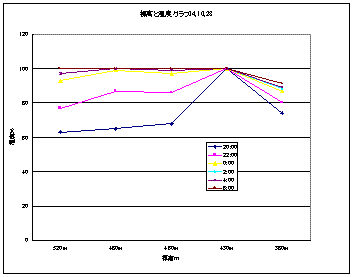
図4 標高別の湿度
例えば図4は調査地点ごとの湿度の時刻別のデータであるが、これをみると、標高430mの地点では前夜の20時には100%に達しているが、逆転層と気温の関係から、ここで霧が発生しているとは考えられない。結局、湿度のデータは分析困難と判断して、深く追わないことにした.
ただ一つ、駒澤観測所の6時の湿度が90.3%以上であれば霧は発生しているが、90.2%以下ではもやが発生するだけで視程1km未満の霧にはなっていない.
(3)風速
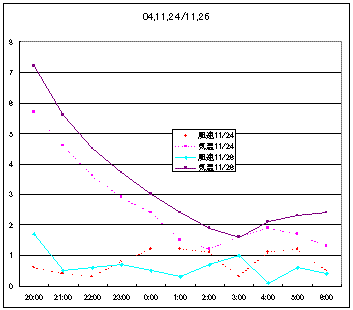
図5 気温と風速 破線は11/24で実線は11/28
風があるときには霧は発生しない.では、どのくらいの風になると霧の形成が妨害されるのだろうか.
風力をあらわすには気象庁(ビューフォート)風力
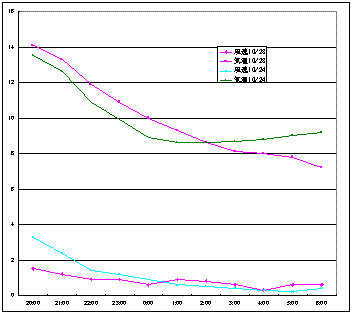
図6 風速と気温10/23(霧)、10/24(霧なし)
階級表がよく使われている.気象庁の風力1は風速0.3~1.6m/s未満、風見には感じないぐらいで、風力2は1.6~3.4m/s未満、風見が動き出して風に感じるほどとされている.
駒澤観測所のデータによれば、霧が発生するのは、前夜の20時から翌朝の6時までの間、この気象庁の風力階級が1以下であり続ける場合である.
ただし、風力が1以下であっても必ずしも霧が発生するわけではない.なお、前夜の21:30ごろまで風力2の風があると逆転層は形成されるが、視程1km未満の霧は発生していない(10/24、10/28).
また、前夜20時の風力が1.7m/sであった11/26には霧の発生が遅れていることからも、「風力階級1以下」は霧の発生にとって欠かせない条件の一つと思われる.
参考までに図6に10/23・10/24の場合を示す.10/23には3時ごろから霧が発生し始めているが、10/24は逆転層は出来ているが霧にはなっていない.朝6時、川路の城山から見ると、煙が棚引き(逆転層あり)、神之峰の奧にもやを確認できただけであった.風とは関係は無いが、この日の気温がなぜ1時ごろから上昇し始めているのか.このことについては後で触れる.
(4)気温の逆転層
(4-1)盛土地域の逆転層

図7 川原の焚き火(12/1 朝7時ごろ)
12/1は濃霧注意報が出ていたが、降霜のためか図7・8の写真にみるように空振りに終わっている.しかしサンヒルズの煙はまっすぐに昇っているが、川原の煙は横に棚引いているので、低いところには逆転層

図8 サンヒルズの煙(12/1 朝7時ごろ)
ができていることがわかる.
このことを観測データでみると、図9のようになる.
高さ別の気温を時刻ごとにつないだもので、例えば20時のグラフをみると、標高400m~450mと480m~520mの間は、上層ほど気温が高い.気温の逆転層ができていることがわかる.
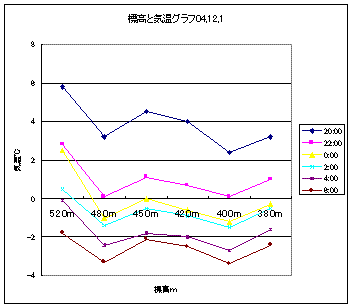
図9 気温の高さ分布(12/1)
図7の写真は、標高400mの地点で煙が棚引いていて、下層の逆転層をとらえている.この日、川路の城山では竜東側に2層のもやを確認している.いずれも逆転層のすぐ下の層に当たる標高400mと480mの高さに淀んでいるものと思われる.
(4-2)霧と最上段の逆転層消失
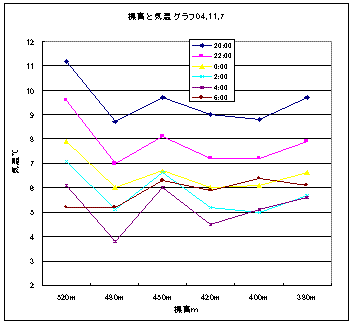
図10 気温の高さ分布(11/7)
水蒸気を飽和状態ぎりぎりまで含んだ空気が、より
低い気温の空気に触れれば霧が発生する.言いかえると、冷たい空気が下方へ降りてきて気温の逆転層が形成される時に霧が発生する.今回の調査でも、霧が発生しているときには必ず逆転層が形成されている.しかし逆に逆転層があれば必ず霧が出るとは限らない.むしろ逆転層が形成されているのに、霧が出ない場合の方が多い.
ここで逆転層と霧の特徴的な関係をみていきたい.
まず、霧が発生している11/7の気温の高さ分布(図10)によると、①2時~4時に最も気温の低い標高400mの地点で空気中の水蒸気の液化が始まり、4時~6時では最高地点以外の標高480m以下の各地点で霧が発生している.このことは、水蒸気の潜熱が解放されることによって気温が上昇していることから知ることができる.②6時になると逆転層は弱まっているが、特に、最上段の逆転層は消えている.これは逆転層のすぐ下の部分で潜熱による昇温があるためと考えられる.逆転層の消失で、霧はゆっくりと上昇しつつ、上昇につれて周辺の気温が低下するので水蒸気の液化が進み、一時的に霧が濃くなるものと思われる.言い換えれば、ここでは霧が発達しているということができる.
同じような例を図11にあげる.
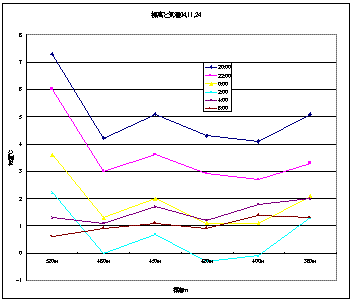
図11 気温の高さ分布(11/24)
この日にも霧は発生しているし、図10と同じことが指摘できるが、違いはただ11/24には霧の発生が11/7よりも早まっているだけである.11/3・11/10についても同様な指摘ができる.
(4-3)下層雲からの放射による昇温
逆転層の消失が2回もあった日がある.11/3の日
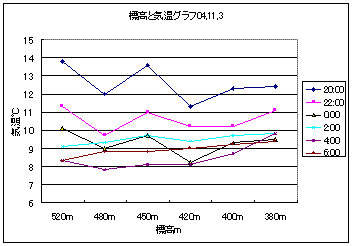
図12 気温の高さ分布(11/3)
で、0~2時までと4~6時の2回、最上段の逆転層が消えている.
0~2時の昇温の原因として考えられるのは、霧の発生か層積雲などの下層雲の広がりである.しかし霧の発生にしては気温が高すぎること、標高の低い方の地点で気温が上がっていることから、下層雲からの赤外線放射で地面が暖められた結果であると判断した.
4~6時の昇温は霧の発生によるものと思われる. 下層雲からの放射によって気温が上昇した可能性の高い例をもう一つあげたい.
図13の10/24の例がそれで、0(24)~2時にかけて気温が上昇しはじめて、以後6時までほぼ同じ状態を維持している.この場合も、気温が8℃以上で高いこと、最高点の520m地点以外のずべての地点で気温が上昇していることから、下層雲の放射による昇温と考えられる.なお、相対湿度をみると、520m地点のみが22時以降の時刻で100%となっている.ここでは霧は発生していない.
なお、この日には朝の6時に雲量7ほどの層積雲を確認している.また、メモによれば神之峰の奧にわずかなもやがあり、煙が棚引いていて逆転層もあることを確かめている.
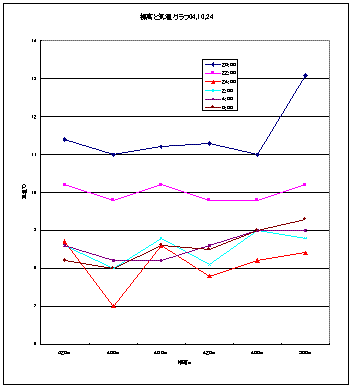
図13 気温の高さ分布(10/24)
(4-4)逆転層が消えていないのに霧
最上段の逆転層が消えると霧になると説明してきたが、最上段の逆転層が消えていないのに霧が発生して
いる場合がある.
11/5の例がそれで、図14のグラフから、4~6時にかけて霧が発生し始めていることがわかる.6時には逆転層は2層とも弱まっており、標高520mの牧場では青空が透けてみえた.
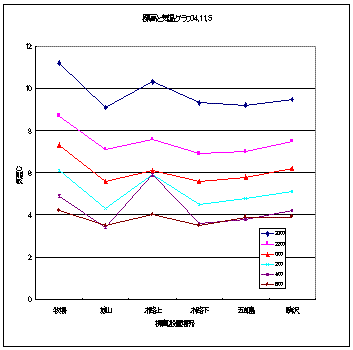
図14 気温の高さ分布(11/5)
これらのことから霧は朝6時以降になってさらに発達して最上段の逆転層も消えたのではないかと推測する.この日のことではないが、同じように霧が深かった日に、朝6時頃から霧が上り始めたということを毎朝川原を歩いている人から聞いたことも傍証になる.
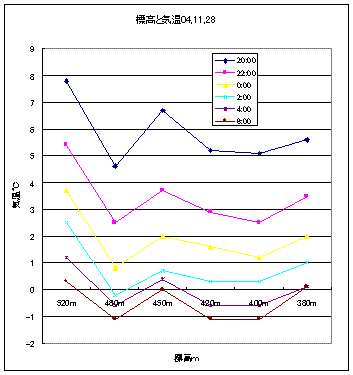
図15 気温の高さ分布(11/28)
同様な例は11/26・11/28でみることができる.
念のために11/28の例をあげる.
この日の朝6時の最高点では霧がなかったし、霧が最も発達していたのは8時ごろだった.このことからも、6時の時点では、まだ霧が発達中で最上段の逆転層もやがて消えていったのではないかと考えている.
(5)結論
川路を中心にした盛土地域で、秋に霧がどのような日に発生したか.その状況をまとめると次のようになる.
①雲はない.
②風は気象庁風力階級の1以下である.
③霧の発生する気温は8℃(10月中旬)~-0.5℃(11 月下旬)と思われる.
④湿度は盛土面で朝6時の値が90.3%以上である.
⑤逆転層は盛土面近くの標高380mから520mの 140mほどの間に2層形成されており、逆転層の下 層で水蒸気の液化が始まるとともに、やがて最上段 の逆転層が消えて霧は発達し深まる.最上段の逆転 層が消えない時には視程1km以下の霧にはならな い.
以上の結果を次のようにまとめた。
盛土地域における天竜川の霧は、日本付近が秋の移動性高気圧に覆われたときに発生する.放射冷却が進んで逆転層が2層できると、逆転層のすぐ下の部分は気温が低くなるので、そこで水蒸気の液化が始まる.霧が発生して潜熱が解放されて気温は上昇する.気温の上昇によって逆転層は弱まり、最上段の逆転層は消失して霧は昇る.下層の逆転層は消えることもあるが弱まりながらも消えないでいることもある.日の出とともに霧は消えはじめるが、下層ではより発達することもある.
(6)おわり
盛土後になぜ霧の発生が抑えられるようになったのだろうか.考えられることの一つは地表面に凹凸がなくなって、霧がたまるところ(冷気湖)がなくなってしまったこと.盛土前、凹地には湿田や湧き水のゆったりと流れる小川があった.ここから霧がわき上がっていったのだろうと思う.
そんな昔のことを思い出しながら調査を進めたが、とくに逆転層がどのように霧の発生にかかわっているのか、いくらかなりとも理解できて胸をなで下ろすことができた.
しかし課題も残る。まず逆転層が果たして二層だけだったのか。温度計の接地密度とも関わって、もっと薄い逆転層を見逃しているのではないか、という懸念。もう一つは、逆転層が形成される位置は何によって決まるのか、という疑問。たぶん傾斜面の地形によるのではないかと考えているが確かなことはわからない。今後、機会があったら調べてみたい。
引用文献
吉野正敏,1961,小気候.地人書館,274p.
小倉義光,1999,一般気象学 第二版.東京大学出版 会,308p.
日本気象協会編,1998,気象科学事典.東京書籍,
637p.
村井忍,1992,下伊那の霧について,飯田測候所
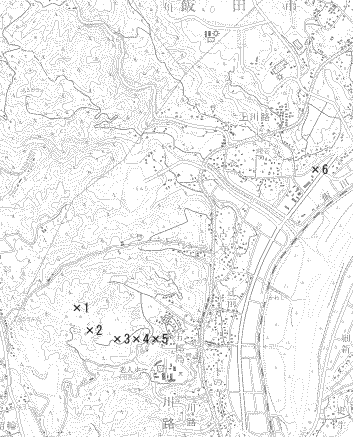 図1 温度計設置場所(1/2.5万図「時又」)
図1 温度計設置場所(1/2.5万図「時又」)
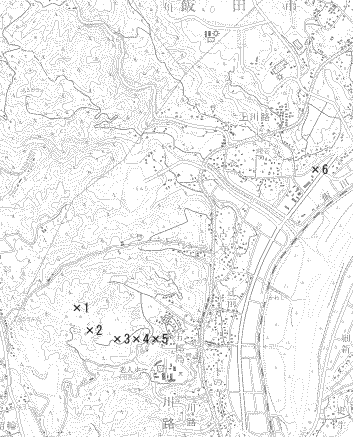 図1 温度計設置場所(1/2.5万図「時又」)
図1 温度計設置場所(1/2.5万図「時又」)
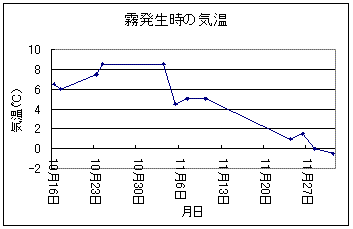 図2 霧が発生したときの気温
図2 霧が発生したときの気温
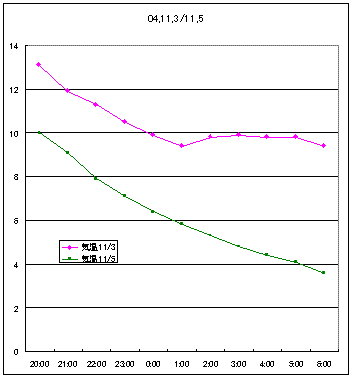 図3 一夜の気温の変化
図3 一夜の気温の変化
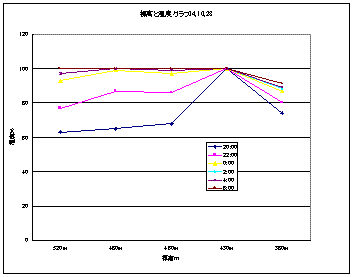 図4 標高別の湿度
図4 標高別の湿度
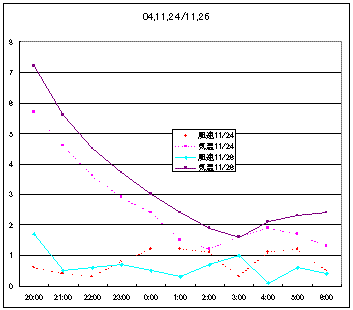 図5 気温と風速 破線は11/24で実線は11/28
図5 気温と風速 破線は11/24で実線は11/28
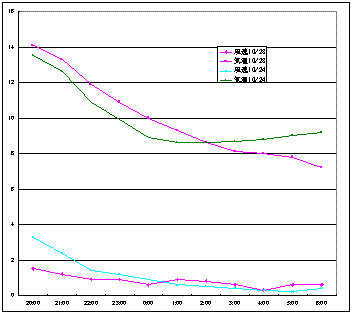 図6 風速と気温10/23(霧)、10/24(霧なし)
図6 風速と気温10/23(霧)、10/24(霧なし)
 図7 川原の焚き火(12/1 朝7時ごろ)
図7 川原の焚き火(12/1 朝7時ごろ)
 図8 サンヒルズの煙(12/1 朝7時ごろ)
図8 サンヒルズの煙(12/1 朝7時ごろ)
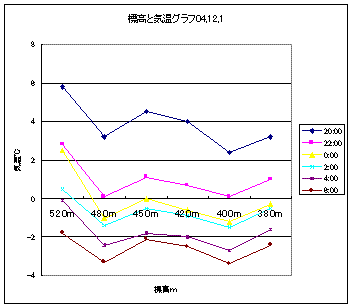 図9 気温の高さ分布(12/1)
図9 気温の高さ分布(12/1)
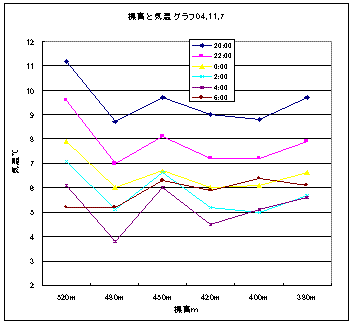 図10 気温の高さ分布(11/7)
図10 気温の高さ分布(11/7)
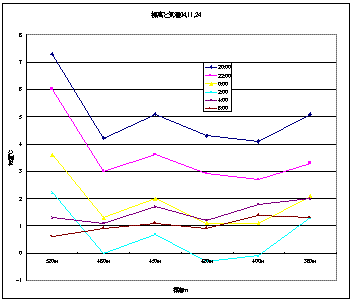 図11 気温の高さ分布(11/24)
図11 気温の高さ分布(11/24)
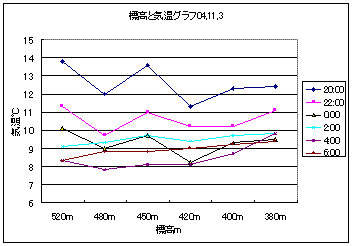 図12 気温の高さ分布(11/3)
図12 気温の高さ分布(11/3)
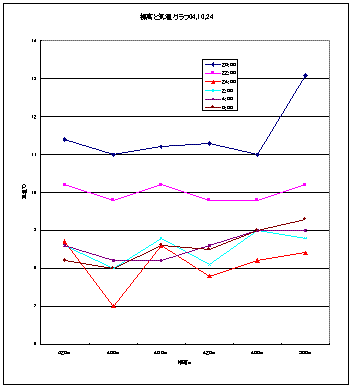 図13 気温の高さ分布(10/24)
図13 気温の高さ分布(10/24)
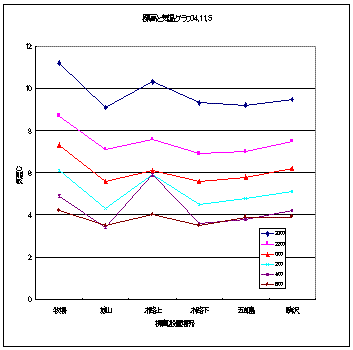 図14 気温の高さ分布(11/5)
図14 気温の高さ分布(11/5)
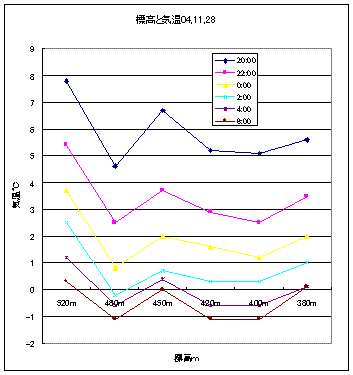 図15 気温の高さ分布(11/28)
図15 気温の高さ分布(11/28)