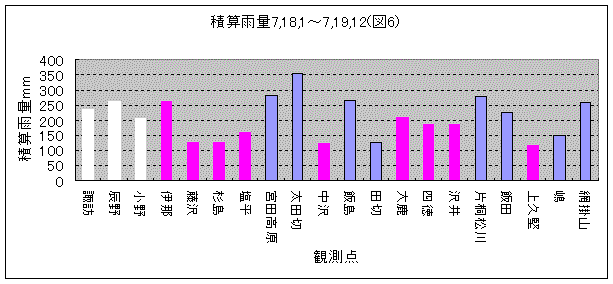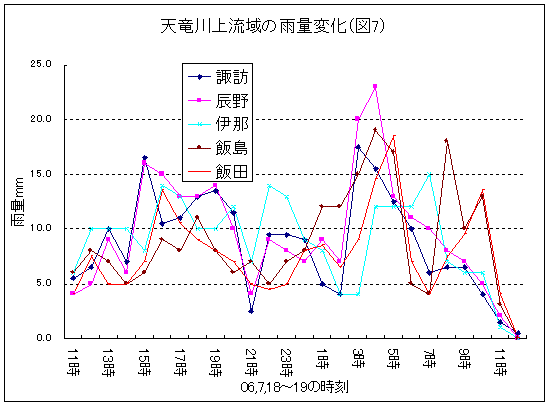平成18年7月豪雨について
【はじめに】
平成18年(2006)7月19日の正午、天竜川総合学習館の大型液晶モニターに映された天竜峡の水位は16.81mを示した。これがこの日の最高水位で、以後、水は徐々に引いていった。
平成14年9月、天竜川上流部川路・龍江・竜丘地区治水対策事業が完成して以来の大満水となったが、時又港(竜丘)やかわらんBAY(川路)に土砂が堆積したこと、堤外地のマレットゴルフ場(龍江)が埋まったことぐらいで、殆ど被害らしい被害は出ていない。
しかし、天竜峡の水位観測点のデータから最高水位を見ると、次のように戦後4番目の大満水であることがわかる。
第1位 昭和36(1961)年6月 20.26m
第2位 昭和58(1983)年9月 19.67m
第3位 昭和45(1970)年6月 17.23m
第4位 平成18(2006)年7月 16.80m
そこで、今回の7月豪雨が数十年に一度の大満水であることを確認し、記録を残すことにした。
【天竜川上流部の水位変化】
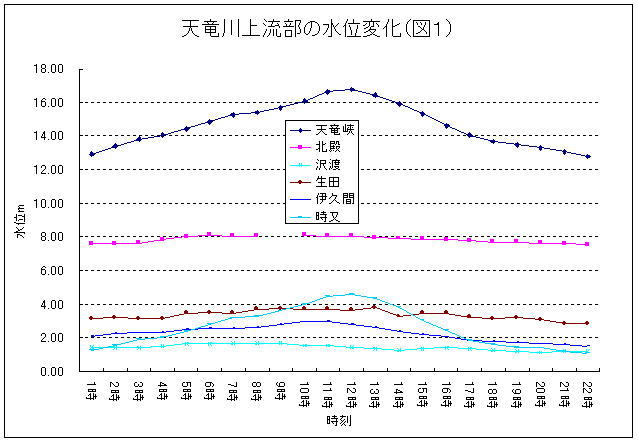
図1は天竜峡以北の主な天竜川水位観測点における水位の変化をグラフ化したもの。このグラフからは次のことがわかる。
①水位変化でピークが見られのは、伊久間・時又・天竜峡で、それぞれのピーク時は11時・12時・12時となっており、ピークの位相が伊久間から天竜峡まで1時間で伝播していることになる。伊久間の観測点は飯田松川の合流点より下流にあり、伊久間の水位変化は飯田松川の水量の変化を反映しているものと思われる。
②北殿・沢渡・生田では水位変化にピークが見られない。これは、北殿では釜口水門、沢渡では美和ダム、生田では小渋ダムで放流水量の調整が行われているためと思われる。③伊久間・時又・天竜峡の水位のピークは下流になるほど高くなっている。これは毛賀沢川、久米川等の小支川の水量が大きく影響していることを意味している。
④グラフには現れていないが、この日の出水状況は次のようになっている。
計画高水位超過:北殿
危険水位超過:沢渡、天竜峡
出動水位超過:伊久間
(生田・時又については不明)
【天竜川上流部の雨量】
天竜峡の水位に影響を与えているのは、どの地域の雨量であろうか。図2は3日間降り続いた内の後半に当たる7月18日と19日の雨量の積算量(左側縦軸)と天竜峡の水位の変化(右側縦軸)の関係を示している。
このグラフからは次のようなことがわかる。
①雨量が多かったのは天竜川右岸の観測点で、特に太田切(上伊那郡宮田村)、片桐松川(松川町上片桐)、網掛山(阿智村智里)、続いて飯田(飯田市上飯田)が多い。網掛山の雨は天竜峡の水位には直接に影響はしないが、摺古木山の雨量データがないので、代わりに用いた。
②天竜川右岸でも、田切(飯島町横根山)のように、それほど多くない観測点もある。
③天竜川左岸および天竜川直近では、右岸のほぼ半分ぐらいの雨となっている。塩平(上伊那郡長谷村)、沢井(大鹿村鹿塩)、嶋(飯田市嶋)の観測点がそれ。
【天気の状況】
7月18日から19日までの天気の状況はどうであったか。
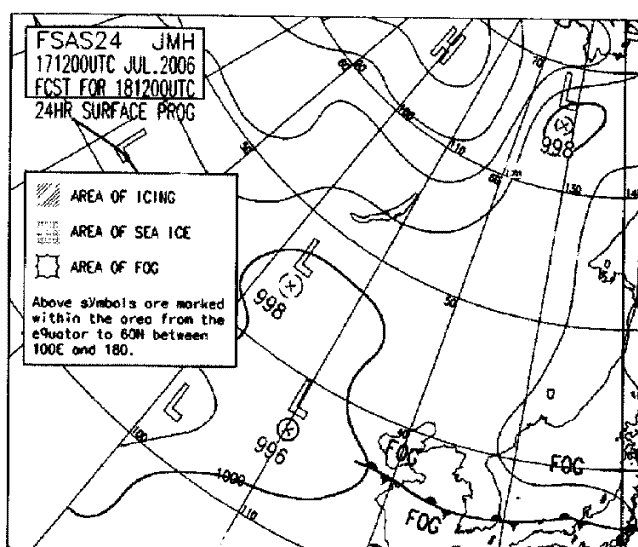
図3 7月18日午後9時の予想天気図
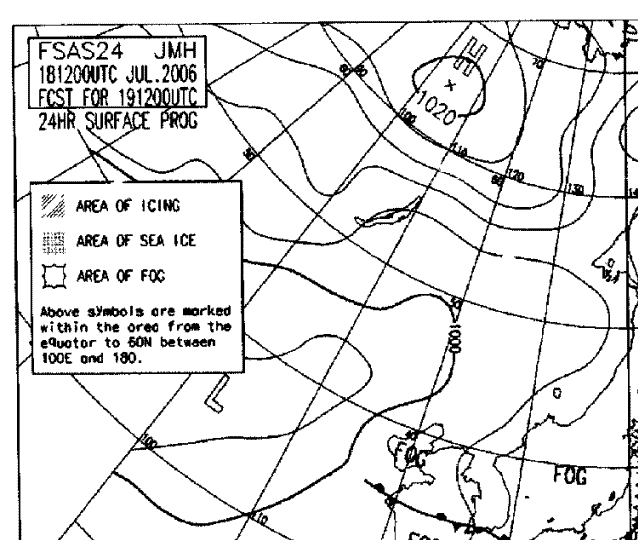
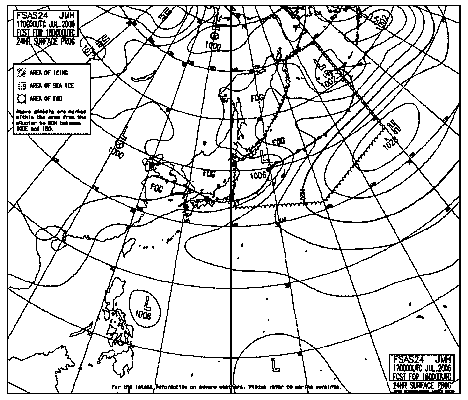
図4 7月19日午後9時の予想天気図
図3と図4に天気図を示す。梅雨末期で、それまで北陸地方に停滞していた梅雨前線が活発化しながら、長野県を縦断し遠州灘へゆっくりと南下している。この前線上を低気圧が発達しながら東進し、この低気圧に向かって南から暖湿気塊が流れ込んでいるが、梅雨前線の南側で、この暖湿気移流と太平洋高気圧の縁辺流とが収束して積乱雲や積雲などの対流雲を発達させたものと思われる。
7月19日の天竜峡で最高水位をもたらしたと考えられる雨量の積算量を示すと、図5のようになる。これをグラフ化したのが図7である。図6では諏訪湖と天竜川上流の辰野町は白抜きで、天竜川左岸の竜東地域は色塗りで、天竜川右岸の竜西地域は黒枠付きの棒グラフで示してある。
この表とグラフから次のことがわかる。
積算雨量が多いのは伊那市以北(伊那の観測点は伊那市東春近)の上流部と天竜川右岸の竜西地域で、1.5日間の合計雨量が200~280mmに達しているが、天竜川左岸の竜東地域は115mm~209mmと少なくなっている。ただ天竜川右岸でも、田切(飯島町横根山)は127mmと少ない。
田切観測点で雨量がすくないのは、地形による。田切の雨量観測所は西向きの傾斜地にあり、これに対して、雨量の多い太田切の観測所は南向きの傾斜地に、同様に雨量の多い片桐松川の観測点は南東向きの傾斜地にある。このことから、当日は南から暖湿気塊が流れ込んでおり、南~南東斜面で対流雲が発達したためと考えられる。
| 観測点 |
積算雨量 |
観測点 |
積算雨量 |
観測点 |
積算雨量 |
観測点 |
積算雨量 |
| 諏訪 |
237.5mm |
杉島 |
125.0mm |
飯島 |
264.0mm |
片桐松川 |
276.0mm |
| 辰野 |
262.0mm |
塩平 |
161.0mm |
田切 |
127.0mm |
飯田 |
227.0mm |
| 小野 |
205.0mm |
宮田高原 |
282.0mm |
大鹿 |
209.0mm |
上久堅 |
115.0mm |
| 伊那 |
260.0mm |
太田切 |
354.0mm |
四徳 |
186.0mm |
嶋 |
151.5mm |
| 藤沢 |
127.0mm |
中沢 |
123.0mm |
沢井 |
185.0mm |
網掛山 |
257.0mm |
図5 天竜川上流流域の積算雨量(06,7,18 1時~7,19正午))
積算雨量の多かった伊那市以北の天竜川上流と天竜川右岸の竜東地域で雨量がどのように変化したかを、1時間毎の雨量で示したのが図7である。雨量は一様ではない。強い雨は断続的に降っており、対流雲が次々と同じ観測点の上空を通過していることが、この雨量変化から見ることができる。
また、19日の雨量がピークの時刻を図7でたどると、梅雨前線の南下に従って、強雨域が二段になって天竜川を下っていることがわかる。すなわち、最初に、諏訪→辰野→伊那→飯島→飯田と天竜川上流から右岸へと時刻に沿ってピークが移動しており、ほぼ4時間後に、二段目が飯島→飯田へ移っている。
このことは、前線が南下する場合には、天竜川の水位が相乗的に増加していくという危険性があることを示唆する。
【まとめ】
平成18年7月19日の大満水は、天竜峡の水位観測点の開設以来4番目の高水位16.80mを記録した。
17日には北陸地方に停滞していた梅雨前線はゆっくりと南下して19日には太平洋沿岸に到達している。また19日には、この前線上を低気圧が東進している。この前線上の低気圧に南から吹き込む暖湿気流と高気圧の縁辺流が重なって、対流雲が急速に発達して強い降水になったと考えられる。
強雨地域は梅雨前線の南下に従って、天竜川上流の諏訪、辰野、伊那から天竜川右岸の宮田・飯島・飯田と南へ移動している。
天竜川上流各地の水位観測点の水位変動をみると、他の観測点特にすぐ上流の伊久間観測点に比べて天竜峡の水位が急激に増加しており、伊久間~天竜峡間で大量の雨水の供給があったことを裏付ける。伊久間の水位観測所は、飯田松川が合流する場所よりも天竜川のすぐ下流にあり、飯田松川の影響も考えられる。すなわち、天竜峡水位観測所における水位変化がトロイデ火山型になっているのは、飯田松川・毛賀沢・久米川等の天竜川右岸の支川の流量が増加したためと考えられる。
【参考資料】
1.今村真直、天龍峡で見た天龍川水位の変遷、昭和61年、32p
2.川路村誌編纂委員会、川路村誌、昭和63年、600p
3.気象庁予報資料、2006年7月17日~19日天気図
4.気象庁、電子閲覧室(ホームページ)
5.国土交通省、水文水質データベース(ホームページ)
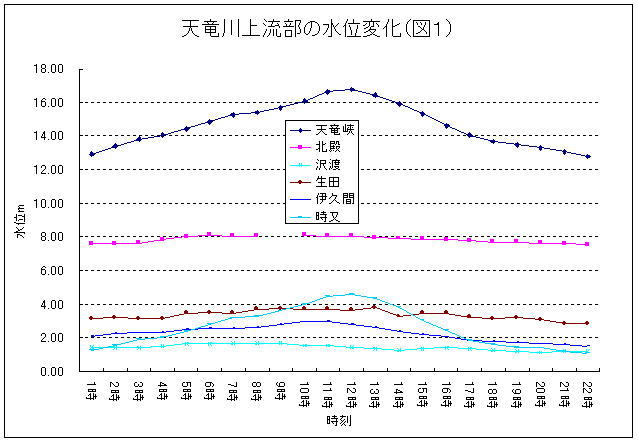 図1は天竜峡以北の主な天竜川水位観測点における水位の変化をグラフ化したもの。このグラフからは次のことがわかる。
図1は天竜峡以北の主な天竜川水位観測点における水位の変化をグラフ化したもの。このグラフからは次のことがわかる。
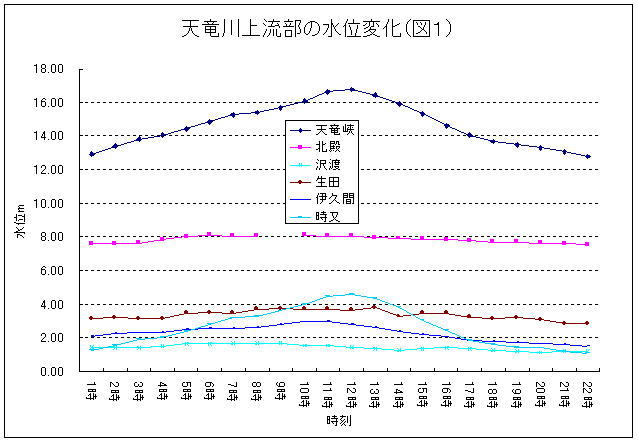 図1は天竜峡以北の主な天竜川水位観測点における水位の変化をグラフ化したもの。このグラフからは次のことがわかる。
図1は天竜峡以北の主な天竜川水位観測点における水位の変化をグラフ化したもの。このグラフからは次のことがわかる。
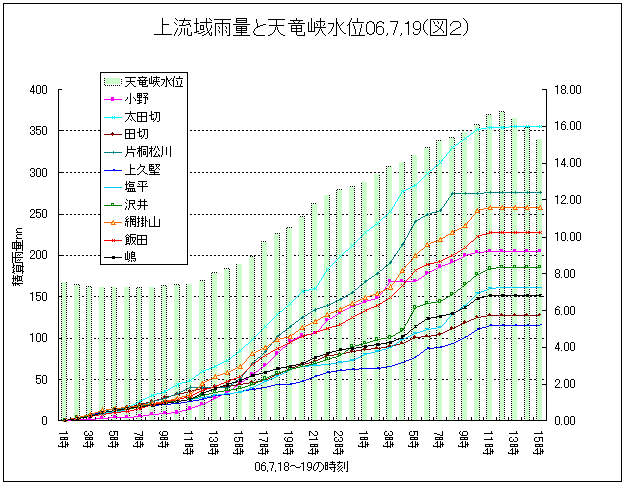
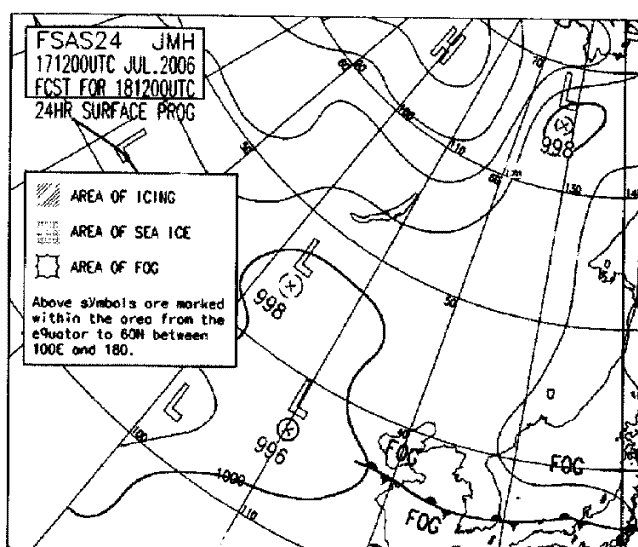 図3 7月18日午後9時の予想天気図
図3 7月18日午後9時の予想天気図
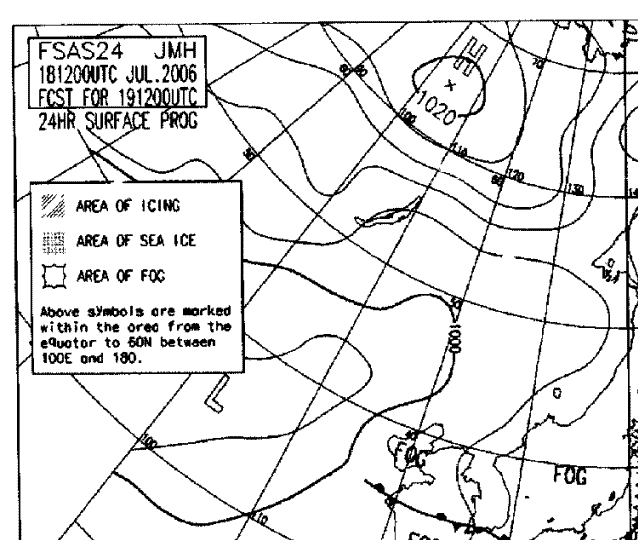
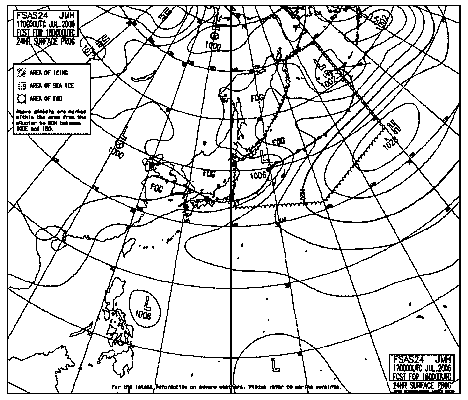 図4 7月19日午後9時の予想天気図
図4 7月19日午後9時の予想天気図