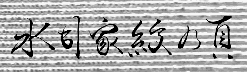三つ巴
(ミツトモエ)

丸に十字
じゅうじ)
家紋 新撰組 島津
紋章と言う範疇の外でも広く用いられているデザイン、シンプルすぎるほどシンプルなデザインの紋章は、どうも家紋としての一般人気が弱い気がします。「巴」は右左、二つ三つに区別無く「太鼓」もしくは「瓦」の模様、「丸に十字」は知らない人にとっては「えっそれ家紋なの?」とのこと・・・丸に十字は、社員がノーベル賞を受賞してその名を轟かせた島津製作所のマークにもあるようですが、とにもかくにもあの「島津家」の紋章です。それはそれは凄い紋章です。
巴紋と太鼓の関連性は大石内蔵助が叩いていた太鼓からなのかな?などと勝手に想像しています。因みに、大石内蔵助は「右二つ巴」だそうです。更には、あの「土方歳三」が左三つ巴とのこと、燃えよ剣での栗塚旭様も、確かに左三つ巴の紋が入った羽織や胴丸を着けていました。
ちなみに巴の左右の判断なのですが、頭の向きで判断する場合と、尻尾の向きで判断する場合とあり、まちまちなのですが、どうやら定説が無いようです。使用家の呼び名と図案に従う以外の方法が無いです。
幕末も差し迫った頃、パリ万国博覧会に日本が参加した際に、当時の政府江戸幕府と、明治政府の中核をなすことになる薩摩藩がそれぞれ参加しました。江戸幕府は日章旗を掲げたのか葵を掲げたのかは記憶に無いのですが薩摩藩は「丸に十字」を掲げたようです。当時のヨーロッパは東洋の神秘の国として日本に興味津々であったようで、幕府のブースも薩摩藩のブースも大変に注目を集め、また佐賀藩も参加していたりで「日本国は連邦国家」なのかと疑われた等、様々に話題を読んだようです。期間中に大政奉還が行われるなど、日本国が真に混迷を極めていた時期ならではのことと言えましょう。
伝え聞く所によると、この頃フランスで馬具製作から様々な装飾品製造を手がけ大いに成功を収めていた「るい・びとん」なる装飾品製作所が、類似品を作られたりしてその対策に大いに頭を悩まされていたそうです。そして、パリ万国博覧会における日本国の評判を聞き、また日本の紋章の事も聞き及んだそうです。そして、日本国の紋章であると目に映った「丸に十字」をモチーフに自らの紋章たる柄を決め、革製品の装飾に大いに用い、他との違いを強く打ち出し、自らの誇りを主張したとのことです。また、その模様は近年の日本においても、主に女性諸君に愛用されるバッグや財布に見られるとのことであります。
獅子の時代と言うドラマがありました、侍(菅原文太)がパリの歴史建造物空間をうろつくのは好きでした。そのドラマの中でのパリ万国博覧会の描写が気に入っています。
このページからは新しいウィンドウです。前に戻る際は閉じてください。
このページヘ直接いらっしゃった方は↓〜メインページへ移動してください。