 初めの始めの御題として選ばさせていただいた家紋は「瓜の中に卍」であります。この紋は長州藩山鹿流軍学師範吉田家の家紋であり、つまり、松陰吉田寅次郎先生御使用の紋として名高いのでありますが、あまり見かけない紋でもあります。
初めの始めの御題として選ばさせていただいた家紋は「瓜の中に卍」であります。この紋は長州藩山鹿流軍学師範吉田家の家紋であり、つまり、松陰吉田寅次郎先生御使用の紋として名高いのでありますが、あまり見かけない紋でもあります。 五瓜に卍 瓜の内卍
吉田松陰 家紋 歴史 水引 飯田
 初めの始めの御題として選ばさせていただいた家紋は「瓜の中に卍」であります。この紋は長州藩山鹿流軍学師範吉田家の家紋であり、つまり、松陰吉田寅次郎先生御使用の紋として名高いのでありますが、あまり見かけない紋でもあります。
初めの始めの御題として選ばさせていただいた家紋は「瓜の中に卍」であります。この紋は長州藩山鹿流軍学師範吉田家の家紋であり、つまり、松陰吉田寅次郎先生御使用の紋として名高いのでありますが、あまり見かけない紋でもあります。
五瓜に卍 瓜の内卍
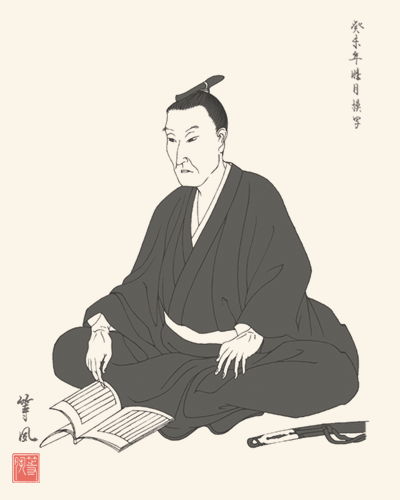
寅次郎先生は、その短い生涯を、至誠をもって貫き通した真の人です。そんな先生は、一個の人間としての誠のために藩命にそむき脱藩の罪を犯しました。そして、そのことのせいで軽々しく本名を名のれない状況に陥られたのでした。先生は偽名を使う必要に迫られ、偽名として名のったのが「瓜の内 まんじ」だったと伝わっております。この「瓜の内 まんじ」の偽名は、かの下田における渡米未遂の際にも用いたと言われているのですが、様々に先生の人柄を考えるとなんとも納得がいくのであります。
先生は兵学家でありましたが、詩人であり、また教育者として歴史上に大きな足跡を残されておられる方です。幼少の頃、それこそ歩き始めの頃から父百合之助より論語を習い、農作業をしながら孔孟の教えを学ばれ、四歳のときに叔父である吉田大助の養子となり、山鹿流兵法を学びました。当時の長州藩は大変に経済的に貧しく、禄を半分にする「検政令」が実施されるほどでありました。また先生の生家杉家はその際に六石取りになったと言われるほど貧しく。養子入りした吉田家もまた太平の世の兵学の家であり貧しかったことは想像に難くありません。そのため農民とたいして変わらない生活の中での学問であったようです。しかしながら、学問に対しての姿勢と、社会の底辺を知るが故の切実な「実行」意識は大変に強く。このことが成人後の先生を決定付けていると思われます。
吉田大助氏は生来病弱であったこともあり、文字通りの命がけで教育を行われた末に、およそ一年ほどで死去してしまわれました。そしてその後はもう一人の叔父で、藩校教授補佐の家玉木家に養子入りしていた玉木文之進から教育を受け、なんと八歳から藩校明倫館で教鞭をとり始めました。まさに天才であったのでしょう。
先生はその後二十歳での九州遊学を皮切りに、日本中を歩き回り、自らの足と目で日本を知り、また多くの出会いを求め、人物との交流を深めてゆくことになるのですが、その過程もまた、「至誠」で貫かれた難儀苦労の道中でありました。前述した、士籍を剥奪されてしまうことになった事件の原因は、東北遊学に際して、友との約束を守るため、旅行自体の許可が下りていたにもかかわらず、過所手形の発行を待たずに出発してしまったことでありました。しかしながら周囲からの不思議な信頼を得ていた先生は、「生家杉家に所属した順士分」として江戸を拠点に自由に学問できるよう配慮されたのでした。かの佐久間象山に弟子入りしたり、水戸学に触れたりしたのはこの頃のことで、天才でありながら謙虚さを兼ね備えていた先生は、素直に学び、真っ直ぐ過ぎるほど影響を受け、感化されました。また感心なことにことに、身に付けた新しい知識、見識を自身の日々の行いに実践しました。その実行のうちもっとも名高いものがいわゆる「下田踏海事件」です。兵学者として、アヘン戦争における清国の敗北等についても深く研究を行っていた先生が、外交問題のみならずあらゆる方面において先行きの見えなくなっている日本国をどのように守り、どのように変革すべきなのかを考えたとき孫子の兵法にある至言「彼を知り己を知れば百戦殆ふからず」にのっとり「諸外国の実の姿」を身を持って体験し、理解しようと思い立ったのは自然であったのですが、なにしろ海外渡航は国禁でありましたので、実行は命がけでした。しかしながらその実行というのが、なんと言うか無鉄砲で、気合だけな行動でありまして、知識もあり、普通の人から見たら何でもわきまえていらっしゃるといって差し支えないほどの人物でありながらほとんど大ボケもいいところな無茶苦茶をしておられるのです。自分が今より若い頃はやはり、先生は世間知らずだったか、観念の世界の住人であったかが故の失敗だったか、という月並みな思慮をしたのででありましたが、長く向かい合って生きているうちに、先生は尊敬しておられた「孟子」に習い、心が濁り、精神によどみが生じるくらいなら、阿呆を覚悟で、人のそしり笑いを甘んじて受けてでも、誠であろうとしたのだと考えるようになりました。考えに考え抜いた末に結局迷いにはまり込み、前にも後ろにもいけなくなって気がつけば地位を得、名声を得、そして知らずしらずの内に獲得した地位と名声に固執するようになって権威、権力に取り込まれてしまい、役に立たない権威、権力のお飾り、権力のおこぼれに預かるだけ(しかもそうなった後ではそのことに気付くことはできない)というのが、世に多くある「偉人」であるわけですが、先生はいわゆる偉人になりませんでした。悲壮な覚悟というよりはむしろ「楽しむ」くらいな気持ちで、どこか底抜けな明るさをもって、一番尊くまた大変な道を選んだのでしょう。下田で密航失敗後敢えて自首したために、珍しい重大犯罪者として人目に触れる、通りに面した牢に収監された際、寧ろいい機会であると、密航に同行すべくともに行動したため、同じく獄につながれた弟子「金子重之助」に講義を行い、また、萩の野山獄に投獄された際には、他の囚人たちを「師」と仰いで教えを受け、自身は「孟子」の講義を行うなどの常識では考えられない前向きで建設的な姿は、悲壮感を漂わしているのとも、能天気故の滑稽とも大分違って感じられるのです。
孔子先生が、混迷を極めてゆく情勢の中で秩序の回復を求めて政治活動に励んだ末に単純に政治や世の中に絶望するのではなく、百年千年先までを視野に教育者となったように、孟子先生が孔子先生に習って政治活動に奔走し、散々な試行錯誤でしかなかったという諦めた悟りでなく、なお「人には善なる性が備わっている」と明るい希望を掲げて、孔子先生に習って百年千年を見据えた教育の道を歩んだように、先生は自らが学んだ松下村塾を再開、主催し、若い人材の育成に情熱を注ぎました。先生の場合は孟子先生や孔子先生の場合と異なって、ある意味政治に触れるような、公の活動を禁じられたからとも言えるのですが、大変に若くして教育の道へ進みました。教え子たちの素質を最大限伸ばし、実際の行いを第一の前提に学識を身につけるという、言うのは簡単であっても行うとなると想像もつかない理想的な教育を実践しました。また教える側において最も大切な「ともに学ぶもの」というわきまえを常に保ち、また共に行うものとして教え子たちと共に幕政、藩政に対しての意見、また実行をおこないました。しかしその実行においてはやはり制限が多く、そのことが先生をして焦燥せしめ、幕府が勅許を待たずに日米修好通商条約を調印するに至って「討幕」の意を表して老中暗殺というテロ行為を画策し、そのために再度萩で野山獄に収監されるに至ったのでした。
先生が生まれてから死ぬまでの三十年間というものは、冷静に考える時間などない、また、誰もが目に見えない何かに押し流され翻弄されていた時代でした。それまで不変であるかのように見えていた社会、制度が崩壊の兆しを見せ、また西欧諸国という初めて経験する外の国からの脅威もあり、正直誰一人として確かな展望を持てず、ヒステリックな熱狂をおびて、誰もが何かをしなければいけないと感じ、様々に試行錯誤を繰り返していた時代でした。そういう時勢の中でできることの中で最善といえることはなんであったか?その答えは、先生が生涯をかけて実践した「至誠」を貫く事だったのだと思うのです。
先生の人柄は、先生の書かれた漢詩や、様々な手紙などから伺われるのですが、雄大で明るく、常に一番大きな、一番本質的な尺度を念頭において判断、行動し、どんな相手に対しても怯まない。また、人の気持ちを大切にし、どんな人とでも気持ちを分かち合って話をする事ができ、相手からあらゆる影響を受け、感化されそして、それ以上に相手を感化し、影響を与え共に向上できる。そんな人物であったと思います。
先生が野山獄から出て松下村塾を主催するにあたり陰の人となるとして「松陰」と名乗られ、若者の教育にあたったのでしたが、時の流れがあまりに大きくうねり、先生は陰の人でいられなかったようです。そして前述の通り、時の幕府の老中暗殺を企て、これまた先生らしいのですが、その案を潘政府に提出したために野山獄に再投獄されました。このいわゆるテロ行為画策は、先生の教え子である久坂玄瑞、高杉晋作にも無謀、無意味であると反対されました。流石に素晴らしい教え子であったと感心する次第なのですが、江戸や京都に出ていて時勢局面の変化をダイレクトに体感しながら判断をした教え子たちと、萩幽囚の身の先生とでは致し方が無いことだと思われます。この時先生は初めて行動の場から離れた場所で思慮し、改めて一人の人間としてより深く掘り下げて思索した末、一つの「思想」的な考えに至ります。「草莽崛起、豈に他人の力を假らんや。恐れながら、天朝も幕府、吾が潘も入らぬ、只だ六尺の微躯が入用」の文章で知られる草莽屈起諭であります。常に実行する方であった先生の残した理論と言えるものはこの一つに尽きると思われます。
安政六年、萩野山獄にあった松陰先生は「安政の大獄」に連座して、江戸に召喚されます。その際松陰先生は門人一同に決別の辞を示しました。「至誠にして動かされざる者未だこれあらざる也。吾学問二十年、齢亦而立、然れどもいまだこの一語を解する能はず。今茲に関佐の行、願わくば身を以てこれをためさんと。すなはち死生の大事のごときは暫くこれを置かんと」
孟子にある「至誠を以って向かうなら、どんな者でも必ず心を動かすことが出来る」という言葉について、二十年の学問を積み、三十歳まで生きてきたが、まだこの言葉を真に理解できたとは言えない。と自らの至らなさを挙げて、さらに江戸召喚に際し、取り調べの場において、命を懸けて自分の至誠を貫き、その誠の心で幕府を始め日本を動かしたいと言う決意を表したのでした。
松蔭先生の容疑は、梅田雲浜の萩来遊時面会し、いかなる話しをしたか、の一件と、京都御所内に落し文をした者あり、の一件であったようで、共に申し開きがたち、召還にあたっての容疑については有罪になるようなことは無かったのでしたが、これまでの人生でもそうであったように卑怯な事が嫌いで、その上決意あっての江戸行きでしたから、自ら死罪に値する事を二つしているのだと切り出し、老中暗殺の計画他自らが画策したことを敢えて評定所において打ち明けました。結果としてやはり死罪が確定し、松陰先生は伝馬町揚屋獄において門弟たちに意志を伝え残すべく「留魂録」を書き記し、その翌日に斬首され、短くも尊く重い生涯を閉じられました。かの首切り浅右衛門は「十月二十七日首をはねた青年の有様は他の誰よりも見事で潔いものだった」と其の人を誰とも知らず語ったそうです。
死を覚悟しての日々、先生が父、兄、叔父に宛ててだした手紙は、 平生の学問浅薄にして至誠天地を感格すること出来申さず非常の変に立ち至り申し候・・と己についての反省からはじまり、また事態は必ず善い方向へ向かうとの確信を書き、最後は 随分御気分御大切に遊ばされ御長寿を御保ち下さるべく候 と父兄等へのいたわりの言葉で締め括られております。また、弟子の高杉晋作に、前に問われ答えていなかった「男士の死すべきときは・・」の問いに死を目前にして発見した答えとして「死は好むべきにも非ず、亦悪むべきにも非ず、道尽き心安んずる、便ち是れ死所。世に身生きて心死する者あり。心死すれば生くるも益なし、魂存すれば亡ぶるも損なきなり。」「死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし。」と書き送っています。そして留魂録のなかで「今日死を決するの安心は四時の循環において得る所あり・・」と死を前に心が安らぐとの境地を述べ「十歳にして死するものは十歳中自ら四時あり。二十は自ら二十の四時あり。三十は自ら三十の四時あり。五十、百は自ら五十、百の四時あり。」と、四時つまり春夏秋冬の季節の巡りが巡って、一つの区切りが終えるべくして終わるように、生涯というものも一つの循環を終えて、終わるべくして終わるものであると言う悟りに立ち、春に芽吹き、夏に伸び盛り、秋に花開き実り、冬に枯れ果てるように、人それぞれに死までの間の成長と実りがあると述べて「儀卿三十、四時已備わる、亦秀で亦実る、其秕たると其粟たると吾が知る所に非ず。若し同士の士其の微衷を憐れみ継昭の人あらば、乃ち後年の種子未だ絶えず、自ら禾稼の有年に恥ぢざるなり」と松蔭先生自身も既に四季の一巡りを終える所だが、結果としてどのような物を遺せのたか自らは知ることが出来ない。しかし、自分の志を見てそれを伝えまた受け継いでくれる人がいたなら、自分の生涯は喜べる生涯だと言えるだろう。と書いています。
留魂録には、まるっきりな「水戸学的尊皇攘夷」思想的な事も多く書かれているのですが、其れを以って尊皇攘夷思想の人物と考える事は少し違うと思われます。人を真っ直ぐに受け止め、感化を受け、そして感化する松陰先生は、自身の周囲にいた、それなりに国を思い、文字通り命がけで奔走した結果先生と同じく安政の大獄に連座して投獄された若者たちの心意気を受け止めずにいられなくて、またそういった姿を弟子達をはじめとした多くの人々の鑑として伝えたいと感じた、そういった心の反映というのが本当だと思います。
留魂録にまつわる史実として、万一を想定して二通書かれ、一通は確かに直ぐに萩に届いたもののなぜか紛失してしまったが、控えとして書かれて牢名主「沼崎吉五郎」に預けられたもう一通が、おおよそ十五年後に松下村塾門弟であった野村靖氏に届けられ、そちらが現存する留魂録である。という実話があるのですが、牢名主沼崎氏はいわゆる「志士」といった風の人物ではなく、言葉は悪いのですがありきたりな罪人であった様です、しかしながら先生の心意気はかえってこのような「草莽」である人に真っ直ぐに伝わったのでしょう。沼崎氏は三宅島に島流しされ、明治七年許されて東京に戻るまでの、ただならぬ苦難の中十五年も留魂録を守り通し、命がけで約束を果たしたのです。これこそ先生の蒔いた誠の種子が見せた花であり実でありましょう、私はこの事を思うたび胸が熱くなるのです。
先生が常に見習い、手本にしておられた孟子先生という方は、五十を過ぎる頃に政治活動を本格的に初め、七十歳頃に故郷に帰り、教育の道に専念したと伝えられております。
書かれている言葉から伺われる事は色々試行錯誤した末の反省に基づいた逆説的な悟りです。「至誠にして動かされざる者未だこれあらざるなり・・」のくだりにしても、恐らく「自分の誠が足りなかったから、自分は失敗ばかりで終わるんだ」と伝わってくるのです。
多くの言葉を通じて「心」が良くなる事の大切さを説き、「目に見えることに対して目に見える結果を出すような事を考え、行ってみても、場当たりなことはその場をどうにかするだけで本質的解決はせず、結局問題は繰り返されるだけだ」と、権力との関わりの中で経験したと思われる本音を繰り返し語り、権力の側に立とうとした事もある自分の反省をある種の自虐ギャグ的に伝え、政治に関しての結論として「民を貴しとなす」と述べ、後にレボリューションの訳語として用いられる「革命」という言葉を書いています。
一人一人の心を動かす「誠」をまず自らが実践する事だけが、本当に建設的で現実的な解決であり進歩だ、という「悟り」を自らの反省を根底にすえて、歴史上のことから日常の事までの判りやすい例を用いて教えることで、至誠を持って生きてゆく人が一人でも多く世に現れる様努力しました。この「悟り」の伝承こそが孟子先生の生涯であると思われるのですが、その意味で松陰先生はまさに孟子先生の悟りを、実際に行った方でしょう。
松陰先生は、生涯に主に三つの名乗りがありました。一つは寅次郎、次にうりのうちまんじ、そして松陰であります。寅次郎は実の両親からの名であり、うりのうちまんじは、脱藩の罪を犯したためにおおっぴらに本名を名のれなかった頃、東北旅行出発から、下田踏海事件の頃までに用いていたと思われる名乗りであります。そして松陰は、萩野山獄釈放後、松下村塾再開の頃、松下村で、陰の、ひっそりとした人となるという意味で用いた名乗りであります。
考心ある松陰先生が、本名寅次郎を大切にしていた事は、生涯の何時においても同じでありました。「うりのうちまんじ」の名乗りは、恐らく本来の名を名乗れない中で、卑怯、偽り、不孝、不忠が嫌いな先生が自らの義を曲げることなく生きられるようにと、自らに連なる由緒、責任、役目を象徴する「毛利家軍学師範吉田家の家紋」から名乗りを考えだして産まれたのでしょう。先生らしい明るさ、詩人らしい遊び心が感じられます。
陰の人となる意をこめて名乗られた「松陰」の時の先生は、ある種の影を背負っておられる節があります。身分が低かったため萩への護送道中ひどい扱われ方をされて病をこじらせ、萩においてもまた身分の低いものの牢獄、岩倉獄に収監され程なくして死んだ「金子重之助」のことは、先生に様々に重い物を残したのではないでしょうか、其れまでには無い自虐に近い程己に厳しい言動、自ら死を望むかのような無謀に近い挙動、確かに誠であろうとしたなら、自分に対してより厳しくせずには居られません。責任感があるからこその敢えて選ぶ茨の道だったと思います。
自分が一番に好きな先生は、「うりのうちまんじ」君です。人間寅次郎さんも、松陰先生も、まさに鑑であり師でありますが、「うりのうちまんじ」君の、未知なる物への恐れも不安もあり、重くのしかかる責任、危機感もあるなかで、雄大な希望にあふれ「欧羅巴・米利幹の風教を聞知し、乃ち五大洲を周遊せんと欲す」と、自らが実際に世界を見、歩き、理解しようと考え、誰に頼むでもなく自らの心と体をもって実行に踏み切った姿は、親しみや憧れを持って心に浮かぶからです。まんじ君には世界に飛び立って欲しかった、そして金子君と一緒に世界中の色んな国の色んな人と出会い語り合って欲しかった、そうして世界中の心から感化を受け、世界中の心を感化して・・・もしそうだったら、世界はもっと・・・・色々な空想が頭をよぎり、寂しさに似た感情が胸を塞いでしまいます。
人は、それぞれにもって生まれたものも状況も様々に異なり、闇雲に誰かの生き方や、やり方を真似してみても必ずしも良いばかりではないです。しかし、心構えは、思想とか、手段とか、様式、立場等を問いません。松陰先生のような生き方、やり方はとても無理だし、真似したところで出来ようが無いですが、先生の心構えを見習う事はきっと、ほんの少しにせよ出来るように思えます。「誠」の心構えがあれば、きっと後でよい事の芽がでます。誠が蒔いた種は、その場では見えなくても必ず芽を出し、しっかりと伸びてゆくのだと証明してくれた先生を思い。その場その場どんな風に目に見える結果がでるにしても、その時その時の結果を超えて、時を経て花開き、実り。時を越えて伝わるものが産まれる事を常に心において、日々僅かずつでも誠を心がけ、ここぞと言う場に向かう時には強い「誠」の心構えで臨めるよう努力したい。そう思う次第であります。
「うりのうちまんじ・五瓜に卍」という家紋は、自分にとって一番に思い浮かぶ紋章です。これほどまでに熱く、また純粋な魂の持ち主に愛用され、孝・忠・義といった最も大切な人間性の所以から名乗りに使われた家紋はそうそうあるものではないでしょう。紋章一つにも至誠を貫く。また至誠を貫くにあたっての心のよりどころとして紋章があった。そう考えています。この紋章は「まことのこころ」を思い起こさせてくれる紋章とさえ言えるでしょう。
紋章というものは図であり、文字に似たものであります。文字同様、形であり型であるわけですが、文字が文法に従って綴られることによって情報を伝達し、更には感情や心、思いを伝えるのに似て、紋章には、伝えたい思いや願い祈り、歴史を込める事が出来るのだと、さらに家々に、また広く世に伝えられてきた紋章には有形無形の気持ちや歴史が込められているのだということを、私が初めて思い知らされたのがこの紋章だったので、第一にさせていただきました。長い長い文章に付き合っていただき本当にありがとうございました。