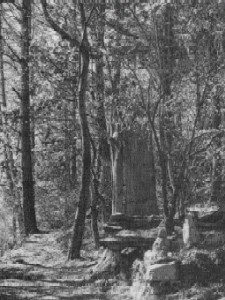|
| 和田から合戸峠の二本杉を望む |
柳田国男が東国古道と呼んだ秋葉街道は、古くは諏訪道と呼ばれ中央構造線に沿って諏訪と遠州を
峠と峠で結ぶ信仰の道として開かれ、杖突、分杭、地蔵、青崩という峠の間には遠山、大鹿、高遠の
集落がそれぞれの肥沃な地味によって形成されていきました。(後藤総一郎著 神のかよい路から)
峠のもとの意味は、「たわむ」(撓む)ところを越えていく、「たわごえ」にあったのでは、と
柳田国男は書いていますが、峠は食料を、信仰を、文化を、そして疫病までも運んだのです。
谷間に住む人々は峠に地蔵を建立し、大わらじを飾り、隣の村から疫病などの入るのを防ごうと必
死にまつりました。
それほど人々に大切にされ旅人が難儀した峠道も、戦後急速な道路網の発展により状況は一変し、旧
道は廃れ、野の仏と寂しく草に埋もれていったのです。
それでも最近になり、杖突、分杭、地蔵峠は自動車道が開き青崩峠はハイキングコースとして整備
が進み、それぞれに脚光を浴び秋葉街道の復活に一役買っています。
合戸峠。
和田と木沢を結ぶ小さな峠で、辞職峠の小川路峠、女工哀史の青崩峠と違って印象の少ない、
いわば無名の峠ですが、かつてこよなく愛した人もいました。
昭和二十(一九四五)年十二月木沢小学校長を拝命し、昭和三十一年にはアルコール爆発事故
(昭和三十年十一月十二日発生)処理のため和田小学校長に復職した、故池田寿一先生です。
「一九四五年十二月三十一日、わたしは待望の峠に登り立って実に感慨無量であった。
汗も覚えぬ間に平凡に頂きに達してしまったが、杉の老樹の群立つところ手向けの小祠の他何も
ない。一人枯草にさす夕日が赤い足のもとに、合戸峠を意識しつつ敗戦の年を送る心持ちは今言
い尽くし難いものがある」
「わたしの父も越えたし、弟も越えた。もとは峠の茶屋もあったという。かつては大平小州も片
桐三省も往きすぎた道である。向山雅重さんや竹内利美さんが探訪の旅も、市村咸人先生・福島
豊先生等史跡調査の旅も、さては井深勉さんや自然調査・地理調査の人たちの、幾度となき往還
―― 一筋の細道にそれらの足跡は深く埋もれていることであろう」
と先生は「遠山紀行」(昭和四十一年発行 編著者池田寿一)に記されています。
村内には数少ない真言密教の本尊「大日如来」が祀られている合戸峠の傍らには、遠山谷のシン
ボル的な二本の杉が長いながい歴史を見下ろすかのように、空に向かってそびえ立っています。
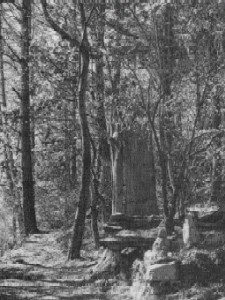 |
| 合戸峠 |
 |
| 峠の大日如来の石碑 |
次の作品へ