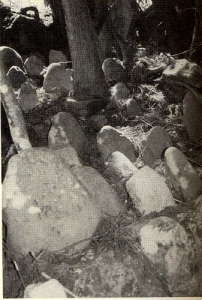
| 庚 申 講 |
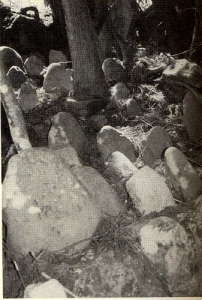 |
| 小道木の百体庚申 |
子どものころ、五円玉を握りしめ、「庚申講」に行きました。
昭和二十五年ころのことです。
当時講を組織していたのは七軒で、その家の子どもたちが二カ月に一度、
庚申の日の夕方、宿に当たった家にお金を持って集まりました。
宿は輪番制で、庚申さま(青面金剛像)の掛け軸を床の間に飾り、だんごと酒を
供え簡単におはらいをしたあと、だんごやちいちのまんま(味ご飯)などを食べ
たりして夜おそくまで楽しく過ごしました。
和田町内にはほかにも何組かの講がありましたが、このような子どもの祭では
なく大人の祭りでした。
庚申講は、昭和三十年代まで全国各地で盛んに行われており、仏教では帝釈天か
青面金剛を、神道では猿田彦をまつっていました。講には家単位で加入し、
血縁関係とか隣組、あるいは有志で組織されていました。
庚申信仰は、道教の影響によるところが大きく、修行道士は、庚申(かのえさる)
の日を守庚申といい、徹夜で修行しなければならないとされていました。
それは庚申の夜には、三尸(さんし)(道教でいう人の腹の中にすんでいるといわ
れる三匹の虫)が寝ている体から出て天に昇り、天帝にその人の罪悪を告げられ
るからだと信じられていたからです。
として民間に広がったものと考えられています。
室町時代末期になると、各地で庚申供養塔が建てられるようになり 申待(さるま
ち)(庚申待ともいい庚申祭りの意)が、猿の信仰と結びついていきました。
その結果、三尸の虫が三猿に置きかえられ、見ざる・聞かざる・言わざるのこと
わざが生まれたといわれています。
忘れられた庚申講ですが、和田地区で復活したところもあり、また下和田地区
では、現在も女性たちにより講が続けられています。
 |
| 青面金剛の掛け軸 |