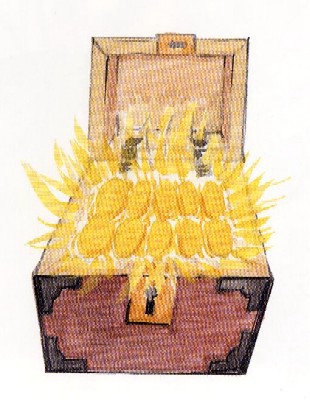
|
愛宕神社の宝物(あたごじんじゃのたからもの) |
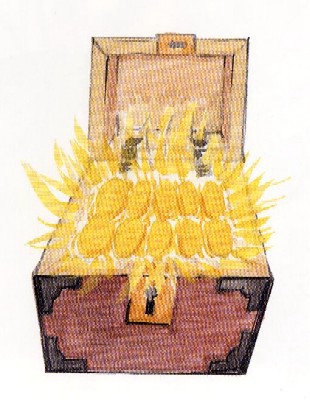 |
どこへいっても、宝さがしの話はあるが、たいがい宝のあったためしがない。
この話も、あてになることじゃあないと思ってきいてくんな。
たとえば、木沢の八幡社には、遠山のお殿さまとその子どもの加兵衛景重の
両大神がまつられとるが、この二人がもっておった宝物が、八本目の柱の下に
うめられとるっていうが、どれが一本目だか、だあれもわからん。
この愛宕神社の宝物っちゅう話も、それをねらっておるということだ。
ある時、このちかくで道普請があり、人夫がこの宝物のことをどっかできい
てきて、もう一人にはなしたと。
「この愛宕さまの下に、よろいかぶとやら、剣やら黄金など、どえらい宝物が
うまっておるっちゅうぞ」
「そんな話、だれでもしっておって、とっくに掘りだされちまっとるにきまっ
とるわ」
「うんにゃ。そんならすぐうわさになるさ」
「そんじゃあ、こんや、村のしゅうが寝しずまったころ、掘ってみっか」
「よし、やってみっか」
そうだんがきまって、さっそくその夜、二人はつるはしをもってきて、
愛宕さまのまわりから掘りはじめたと。
 |
この愛宕神社っちゅうのは、木沢八幡社の横手の畑の片すみに、石を小高く
つみかさねて、その上に小さなほこらがおいてあるだけのものだ。
「おいおい、なにかでてくるか」
「いんや、なあんも」
「あっちも掘ってみっか」
なんちゅって、掘りかえしとるうちに、ほこらがひっくりかえりそうになっちまった。
「これ以上掘って罰があたっちゃたまらん」
「なんにもなかったように、土をもどして、草も植えておくか」
次の朝、また道普請のしゅうが集まってきて、
「なんじゃこりや。だれか愛宕さまんとこ、掘りかえしたやつがおる」
なるほど、かくしたつもりの草はしおれて、きれいにしたはずの土も新しくて、
掘ったあとがみえみえだった。
そこへ村の古老が通りかかって、
「あれまあ、ばかなやつもおるもんだ。愛宕さまのほこらにかくされとるっちゆう
宝物を、掘らっとしたんずらが、愛宕さまはなあ、もともとこの場所にゃあなかっ
たんだで、いくら掘っても、宝物はぜったいでてこんわ」
と、大笑いしたって。
それでも、二人はゆうべのことがばれちゃあまずいで、愛宕さまのもとの場所を
きくこともできなんだって。
どうだな。なさそうでありそうで、ありそうでなさそうな話ずら。
 離山庚申さま
離山庚申さま