
| 離山庚申さま(はなれやまこうしん) |
 |
横道(下本町)の石段を、すこし登ったとこに高平山(こうへいざん)薬師堂が
あって、そのよこに離山庚申をまつったほこらがあるのを知っとるかな。
霊験あらたかで、いまも願(がん)かけをする人が多いとか。
その話をするかなあ。
ときは明治のなかごろ、山師たちは山の飯場(注)へとまりこんで木を切り
出す仕事をしとった。
遠山の地元のものばっかじゃあなくて、東北や新潟からでかせぎにきておる
ものもおおぜいおって、気もあらく、他人のことなんかいちいちかまっちゃ
おれん雰囲気だった。
その日も、仕事のとちゅうで一人のおとこが、腹痛をおこしたっちゅって、
飯場へ帰っていっちまったけれど、一人へったことで仕事はよけえきつくな
るし、そのおとこのことなんかかまっておれんもんで、みんなそのまんま一
日仕事をして、夕方おそく飯場へ帰ったんな。
「おー、おれの服がねえーぞ」
「ややっ、おれの金がなくなっとる」
飯場は大さわぎになった。
「さては、あの腹痛おとこのしわざだな」
みんな、手に手に松明(たいまつ)をもって、四方にちっておとこのゆくえをさ
がしたけれど、おとこがおらんようになって、まる一日たっておる。
きっと遠くまでにげちまったらしく、まるっきり手がかりがねえ。
そんな中で、和田から働きにきとったおじいが、さがしさがし村の中心まで
きて、ふっと庚申さまのことをおもいだした。
「そうだ、庚申さまにお願いするがいい」
おじいは、離山庚申さまのところへいそいで、
「庚申さま、庚申さま。みんなの服やお金をぬすんだぬすっとを、どうかつまえ
ておくれんかな」
と、頼んだと。
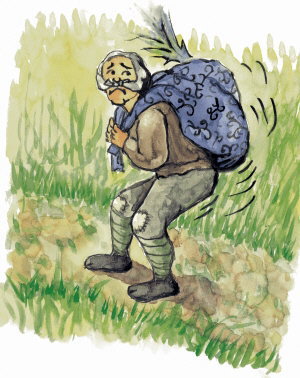 |
いっぽう、おとこはその時分、青崩峠(あおくずれとうげ)をこえて水窪(みさくぼ)まで
きておって、まだその先へどんどんにげておった。
そのとき、急になにか重いものが背中にはりついた感じがした。
重くて重くて、歩くにもやっとになった。
「な、なんだ、なんだ」
背中のぬすんできたものをおろして、あれこれ見ても、なんの変わったこともねえ。
また背負って歩かっとすると、ズシンと重くなる。
そんなことをくりかえしておると、なにか背中でブツブツいう声がした。
うしろをふり返っても、だあれもおらん。
おとこはだんだんきみがわるくなって、はってでもにげっとしたそのとき、
「にもつを返してやれ」
こんどは、はっきり声がした。
これには、さすがのおとこもびっくりぎょうてん、
「わるうございました。にもつを返しにまいります」
大きい声で背中にむかってさけぶと、おどろいたことに急に背中がスッとかるく
なった。
おとこは、ますますおそれいって、きた道をあわててとってかえしたって。
飯場へ帰ると、なかまの前で深々と頭をさげてあやまり、道中のふしぎな出来事
をみんなにはなしたんな。
それをきいたおじいは、庚申さまがきっとおとこににもつを返すようにさせたん
だとおもい、さっそく米だんごとお旗をあげてお礼をしたんだと。
それからも、物がなくなったり、忘れ物がでてこんようなときは、離山庚申に願
をかけると、必ずごりやくがあったそうな。
みんなも、願をかけてみるかな。
そんなときは次のようにいうといいって。
オコウシン、オコウシン、マイタリマイタリ、ソワカ。
これを十五回となえ、オコウシン、といっておじぎを二回。
最後に、
マンダリ、マンダリ、ソワカ。と十五回となえるんだって。
気持ちをひきしめてやらんとだめだに。
そうそう、それからお礼もかならず忘れんようにな。
![]()
(注)飯場…作業現場が人家から遠いとき、その現場近くで寝泊りできるように建てた小屋
 小嵐さまのたたり
小嵐さまのたたり