
| 狐 の 家 族 |
 |
まだ、和田のまちがあんまりにぎやかでなかったころのことだ。
今の役場のあたりも家が四、五軒しかなく、老人福祉センターから、
小池の集落にいく細い道の両側は、桑畑がつづいておって、小池沢
の沢すじには水車小屋もあった。
ある年の春、その近くの岩穴に狐の家族がすみついた。
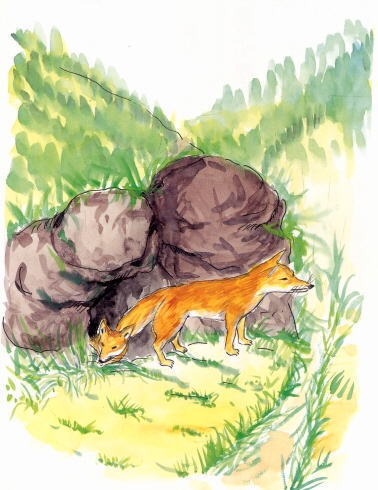 |
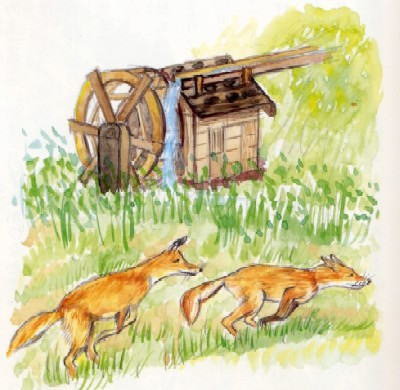 |
そこで、村人はその岩穴を狐の穴って呼ぶようになった。
のどかな村だったもんで、狐の家族ものびのびと暮らしとった。
天気のいい日には、岩の上に小さい猫ほどの子狐がひなたぼっこをしとったり、
水車小屋のあたりまできて、桑畑の中を走りまわっておるのを見かけたもんだ。
それでも、だれひとり狐にわるさをするものもおらなんだし、子どもたちは
かわいい子狐を見たくて、水車小屋のあたりで遊んだり、たまには餌をやった
りしとった。
ところが、秋も過ぎ、冬がくると山の餌が減ってきて、狐が村人の飼ってお
る鶏をとるようになった。
そのころは、どこの家でも鶏を五、六羽は飼っておって、毎朝、
「コケコッコー」
ってときを告げて、村人の一日がはじまったし、卵はすごく貴重なもので、親戚
や近所に病人があると、みんな卵をお見舞いにもっていったもんだった。
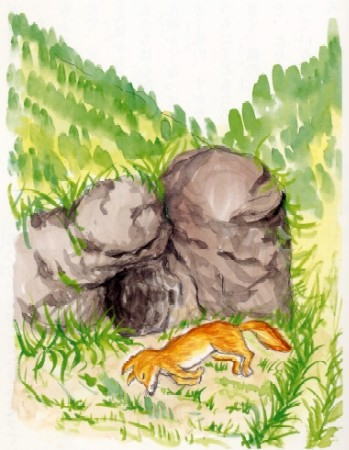 |
そんなたいせつな鶏を狐にとられては、村人もほってはおけんということで、
そうだんしたあげく、トラバサミをしかけることになった。
狐を好きだった子どもたちは、かなしんだけれど、鶏の方がもっとたいせつだ
ってわかっておったもんで、どうすることもできなんだって。
もうちょっとで春になるころ、ついにトラバサミに大きい狐がかかった。
雄だったで、父さん狐にちがいなかった。
「お父さん狐がおらんようになったら、狐の家族はどうしておるかなあ」
子どもたちは心配になって、狐の穴の近くにいくどもようすを見にいった。
どんどん暖かくなっていくのに、ひなたぼっこをしておったり、走りまわっ
たりする子狐の、すがたはいちども見れなんだ。
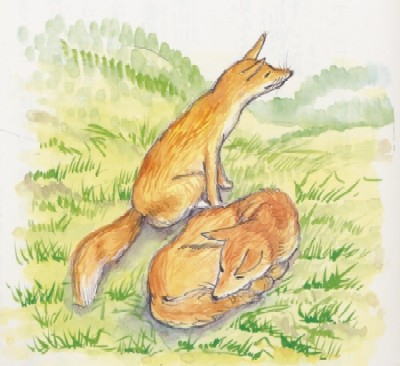 |
そのうちに子どもたちも、だんだん狐の穴の方へいくことがなくなってきた。
秋がきて、狐の穴のちかくのクルミの木のもちぬしが、クルミとりをした。
そのあと、とりのこしたクルミをむちゅうになって拾っていた子どもたちが、
横になっている大きな狐を見つけた。
おどろいた子どもたちは、ぱっとはなれて、しばらくようすを見ておったけれど、
声をだしてさわいでも、石をほおっても、狐はぴくりとも動かん。
おそるおそる寄っていってのぞきこむと、狐は死んでおった。
お母さん狐のようだった。
「わるさがすぎるで、だれか毒をもったんずら」
大人たちは、そんなうわさをしておった。
それでも子どもたちは、
「お父さん狐がおらんようになったで、お母さん狐はさびしくなって死んだんだ」
っていいあった。
もう子狐のすがたも見んようになったが、子どもたちは、
「きっと子狐は、もっと山奥で、元気に暮らしておるにちがいない」
って思っとった。
今でも山奥のどっかで、この狐の子孫たちが、ひなたぼっこをしておるかなあ。
 大入道に化けた狐
大入道に化けた狐