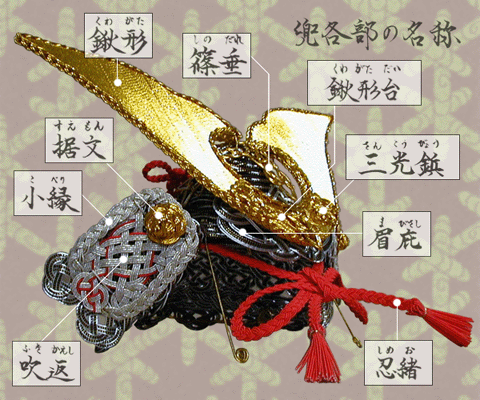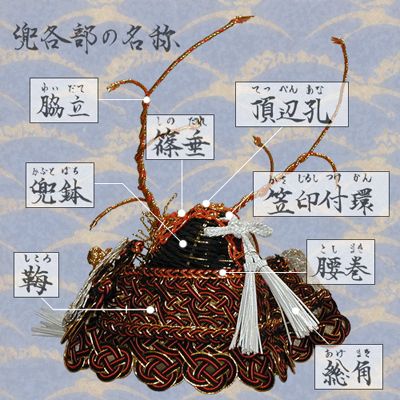さて、その式正鎧には「星兜」を被るものとされております。原色日本の美術の「甲冑と刀剣」にある説明が簡潔でまた整っておりましたので引用させていただきますと
『星兜は鉄地矧ぎ合わせ留めの鋲頭が椎の実形に高く厳しくなっているところからこの名がある。鉢は八枚ないし二十四枚の古式なものから、三十二枚に及ぶ梯形の鉄板金を矧ぎ合わせ鋲留めにして形成する。矧ぎ合わせの板は裁断したままの物から、板金の片側の縁を捻返して引くし筋を立てるようになる。
頂辺に円い孔をあけ、縁に共金の覆輪或いは金銅の葵葉形の座と菊座玉縁を施して八幡座とし、鉢の裾には帯状板金をまわして腰巻とし、星一点ずつを打つのが普通である。そして鉢の左右側面に二ないし四箇所の響孔をあけ、忍緒の先を引き通し結留にし、後中板の上部には笠印付環をうち、揚角をつける。
なお、鉢の前後ないし左右の地板の上に鍍金銀を施した板金を伏せ、篠垂の座をつけて星を打つ。これを片白・二方白・四方白といい、星兜の権威を表わす著しい荘厳である。そして、鉢の正面腰巻板に花先形の鉄地絵韋包の眉庇を三光鋲で留め、鍬形台を打ち、鍍金の鍬形を立てたもの、真向に竜あるいは獅子の前立物を飾るものもある。
革毎(革篇に海のサンズイのないものでシコロと読む)は小札三段ないし五段の鉢付板(一段目)を腰巻に鋲留めにして、古くは杉立形に垂れ、正面両端の部分を後ろに撓めて折り返して吹き返しとし、表面を絵韋で包む。
鎧の著しい装飾として、各種色目威しのほか、金具廻・革所を包んだ絵韋、あるいは袖や草摺・革毎の菱縫板を飾る裾金物・裾文金物・金具廻と小札板の継ぎを飾る化粧板や、鉢付板に打つ八双鋲などがある。
とあります。それぞれの部品には、実戦における効力があり、またそれらには神聖な意義を込めた名が付いている事が判るかと思われます。まず星兜の星でありますが星は古来より現代にいたるまで「神聖」な存在でありまた「運命」を象徴するものであります。兜の鉢の鉄板を留める鋲に「運命を決定するもの」との意味が込められているのです。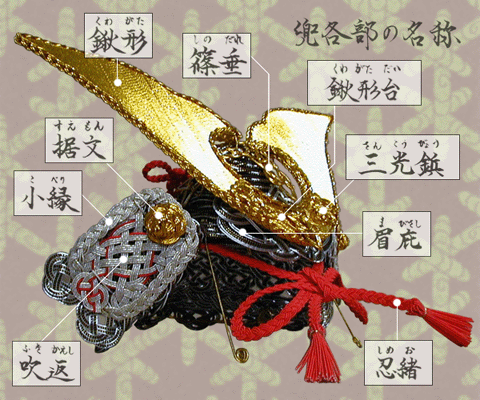
私がかつて愛読した本に所謂「軍記物」がありまして、特に保元・平治物語、義経記が好きで、将門記から平家物語まで多くは現代語訳の本で読みました。信長記などのさらに後世の人物の物も読みましたがさほど熱中せず、高校などに入りましてからは特に気に入っていた保元・平治、義経記等を古文で読み返したりしたのですが、源平ものの合戦場面での描写に、矢が正面から直撃したが、鏃が兜正面の星に当たった為に貫通せずに横に其れ、命拾いし、命拾いした側がその戦の勝者となると言った場面があった記憶もあります。(長い事読んでおらず手元に本がないのでどなたかご存知の方いらっしゃったなら是非掲示板等にご指摘のほど宜しくお願いいたします。為朝が清盛を射た場面でしょうか、また兄弟との戦の場面でわざと星を射て殺さなかったと言う場面もあったようななかったようなすみません・・)
さて、星に込められた意味とその防御面の実用性と異なり、「頂辺(てっぺんと読みます)孔」はそれ自体は髻(もとどり)を入れた萎烏帽子の頂を引出す為、つまり束ねた髪を頭を覆う頭巾の様なものと一緒に兜の頂上から引き出す為の孔で、平家物語の頃には既に髻を通さなくなったようで(髪をほどいた頭に萎烏帽子をかぶる。兜と烏帽子が取れた状態を「おおわらわ」と言います。)すが、その孔の装飾が重要で、前述の様に「縁に共鉄の覆輪あるいは金銅の葵葉形の座と菊座玉縁を施して八幡座とし・・」あり、特別に「格式」の高い装飾を施して、兜の頂上に「日本国の護神で武神」である八幡様の鎮座する場所としているのです。
八幡様は「応神帝」でありまして、武家源氏の正統たる清和源氏が、その権威を高めた「前九年・後三年の役」において活躍した武家源氏の棟梁の中の棟梁「源義家」が京都石清水八幡宮において元服し、八幡太郎と呼ばれた事から、時代を追うに連れて「源氏の軍神」ひいては「武士の軍神」として崇められた神であります。その八幡様が鎮座まします座でありますから、兜がどれほど神聖なものであるかが判るかと思います。
「篠垂」は「星兜の威厳を表わす著しい荘厳」と書かれております通り、ともすれば厳しいばかりになってしまう鉢に添えられた彩りでありましょう。また、八幡座から下がるの物ですから「八幡座」の存在を示す意義もあるのではないでしょうか。
「笠印付環」は、これまた八幡座に属する形で総角(あげまき)や「笠印」(敵味方の区別をつけるための印の類)を結びつける為の環でありますが、総角結びは、装飾結びの代表であり「魔除」の意味を持ち、また、結界がそこにあることを示し神聖な存在がそこにあることを示す意味があったようです。
「眉庇」は鉄地絵韋包、つまり鉄で作ってあり、絵韋すなわち絵柄がプリントされた革で包まれているということで、鉢の「腰巻」(これは鉢と革毎{革篇に海のサンズイのない奴でシコロ}とを繋ぐ部分を強化する為の部分)に取付ける部品です。額を護り、さらにここに鍬形を支える土台「鍬形台」が打ち付けられます。
次に「鍬形」なのでありますが、農具の鍬からきたものとされ、古代の鍬の形をかたどったと伝わっておりますが、農具を兜の正面に据える意義は、恐らく地母神信仰なのではと私は思っておりますが、詳しい事は定かでないです。実用面でのことは正直判りませんが、当時の主兵器である矢の顔への直撃を防ぐ効果がありそうです。鍬形については正直推測でしか物が言えませんが、「大将の威厳」を示す事が最大の意義ではないでしょか。鍬形を止める鋲は星ではなく「三光鋲」と呼ばれておりますが、名前の由来等は、よく判っておりません。
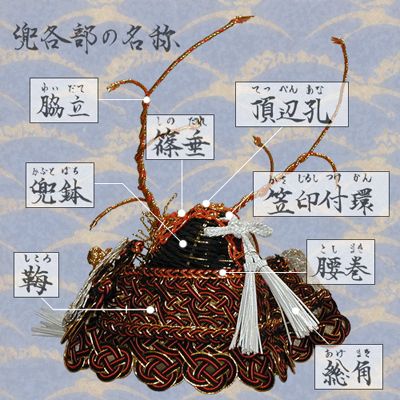
鉢に関しての部品の次はシコロであります。シコロは鎧の他の部分と同じく「小札」と言う革や鉄で作られた小さな板を綴り合わせて作られております。全てを鉄で作る事は機動性を損ない、また防御面でも刃物に強いが飛び道具に弱くなる面があり、全てを革で作る場合も防御面での弱さがありとその組合せ等に様々な工夫があったと伝え聞いております。急所であり、かつ多様に動く首を守る為の重要な防具であります。
小札三段もしくは五段とされ、鉢とは腰巻で接合部分を補強しつつ繋ぎ、正面部分のそのまま伸ばしてあると顔正面を覆ってしまうであろう部分を、左右に開いて撓ませつつ折り返した部分を「吹き返し」と呼びます。ここには絵韋を張りまして、さらに留め金具の「据文」がつきます。何度書きました「絵韋」の役割は、主兵器である弓矢を用いる際に弦が引っかからないようにする為に滑らかな表面のなめし皮が張られたということです。鎧の胴の部分にも張られ、その名も「弦走」(弦走り)と言います。
吹き返しの据文についての意義でありますが、これはと言う例に武田家に代々伝わってきた、源氏棟梁家の源氏鉢領鎧の内の一つ「楯無」と伝わる甲冑の兜の吹き返しの据文には、「花菱」をあしらった金具が用いられていたそうで、これが甲斐源氏「武田家の家紋」の「武田菱」の源となったと言う話があり、着用者の由緒等を主張する意義をもった装飾であったとも考えられます。
また、吹き返しの撓み具合を変えて、顔正面を更に覆うようにすることも戦での状況ではあったようで、装飾としての面だけでなく、実戦での様々な状況変化に応じた防御を可能にする為の工夫であった事がわかります。
さて、このように一つ一つに定まった意義や、実用面の便宜が込められ、高い完成度を誇る星兜でありますが、戦闘の時代から、戦争の時代に移り変わるって行く流れのなかで、戦術も変化したりで、衰退してゆきます。しかしながら、その存在感はたえることなく続き、記録として作成されたはずの戦記物の絵画において、大将はなぜか来ていたはずのない大鎧を着た姿でかかれ、星兜を被っております。また、名のある武将達は皆、大鎧と星兜への憧れの気持ちをどこかで持っていて、それぞれの信念と生き様に合わせたやり方で大鎧をデフォルメし、幾つかの部品を「形骸化」し、只の「飾り」にしてしまいつつも、一個の人としての人生と生き様を反映した、時代時代のその人その人の鎧兜を身にまといました。
そういった「大鎧・式正鎧」の時代以後の時代の甲冑の鑑賞におきましても、大鎧を知った上で、どのような趣味・風潮・地域性、また武将個人の性格・人間性・思想によってデフォルメしたのかを、戦術・戦略面での創意工夫とあわせて読み解く様にいたしますと、楽しみの深さが一段とますかと思われます。
次へ 戻る