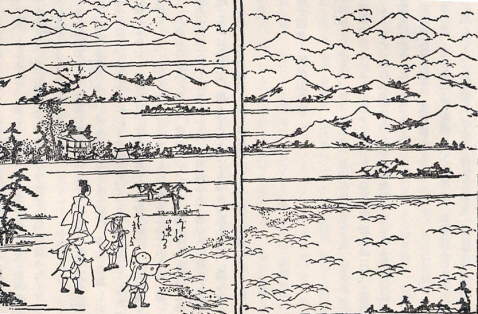
遠山奇談後編 巻之三
第十三章 衣がさき塔のかげ諏訪七ふしぎの事
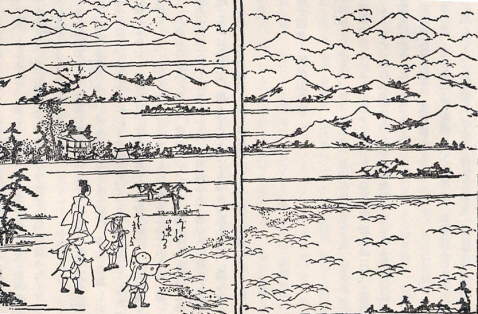 |
遠山のうち、神嶺山濁り澤などは、おく山にて、しかも高し。甲裴信濃を見やるに、手の下
のごとく也。しかるに須波(すは)(21)の海の北山のあたりより、神嶺山ならんなど、あらそ
ひ戯むるゝにつきて、其所の宮人らしきが来合せ、こゝより遠山の神領などあらそひ給ひしか、
いかにも神領也。
しかしあのごとく雲霞に隔てられて、山の像わからず。こゝにふしぎなる所あり。
此所を衣が崎といふて霊地なり。むかふに雲霞にへだてられて、中々目もとゞかず。
皆白雲に見へし所は富士山なり。かの富士こゝよりは雲霞へだつるといへども、此衣崎の水す
みて清々たる時は、かの富士の峯、霞にかくれ、人の目には、見へねども、峯は湖中にうつる也。
今はその時にあらず。四月比山のかひより、湖中にうつるといふ。
不審(いぶかし)く思ひ、押てそのよしを問ふに、いにしへ神代の末に、釋迦如来と加葉仏(かせ
んぶつ)との法衣(ほうゑ)を請うけて、富士の地にうづみ世の富を守り、福田の寶とするとて、
謹で其地に埋めらる、又その衣服をば、今此北濱に、埋給ふ。此縁によりて、こゝを衣が崎と
いふ。
終に富士山繁茂してより、此峯こゝにうつることふしぎ也。衣がさきといふ地名は、いにしへ
よりあれど、人の心濁りて目にかゝらぬ人もあるべけれど、かのうつる時をえて、こゝにいた
り、其霊なることを知るべしといふ。さてさて奇なる哉妙(めう)なる哉と、みなみな感じけり。
今此須波のうみには、いろいろのふしぎなることあり。諏訪の七ふしぎとていひならはせり。
取わけ、ふしぎなるは、上の宮本地堂(22)の透空(すきあな)へ、紙をあてゝ見れば、塔の影う
つることあり。
然るに、塔そのあたりになし。何が塔にうつるやら、其わけ今にしれず。
衣がさきへ富士のうつるは、東に富士あるゆへ、其形ちうつること、めに見へしこと也。
此奇は、形なくして、紙にうつること、いかにもふしぎなり。
これに付て思ひ出せしことあり。十四五年も以前のことなりしが、ふしぎなることを、はじめて見付し事あり。
洛南東寺の南門羅城門通を、世俗四塚といふ。此あたりの人家のことなりしが、其家の表、門口の大戸といふも
のを、闔(さし)て、くろゝの穴より覗けば、東寺の塔のかげ、ちいさく寄麗に見ゆることありしが、今も見へ
けるとぞ。此様子を、人々考へるといへども、何のわけとて、うつることやら、分明ならず。しかし是も東寺の
塔まさしくあるものゆへ、ふしんといへど其體はあること也。須波上(すはかみ)の宮本地堂の透明(すきま)へ
塔のうつるは、さらに體のなきもののあらはるゝは奇といふべし。
しかるに、此諏訪の湖水、いにしへは周(めぐり)六十七里二十一歩とあり。
又洲羽(すは)の七不思議といふことは、一ねに御渡。二つに御作田。三つに耳裂鹿。
四つに社頭の雨。五つに根入杉。六つに塔のかげ。七つに蛙狩(かはづがり)など也。
一つに神渡りといふは、湖水一面に風ひびらいてより、氷鏡のごとく張也。
毎年立冬の節になれば、かの氷かならず一夜にはる。これを御渡といふ。
かくて後は、荷を擔ふものはいふに及ばず、荷馬までも躍ゆくに、少しも危ふきことなく、神
![]() ふしぎの湖水なり。此竪凍(こほり)を狐はじめて渡ることを見て、人皆あやふからずといふ
ふしぎの湖水なり。此竪凍(こほり)を狐はじめて渡ることを見て、人皆あやふからずといふ
て、人渡りはじむるといふは、世俗のいひつたへなれど、さにはあらず。
狐聴レ冰といふから思ひ違ふたるもの也。必狐と思ふべからず。又此氷をうがちて、漁(あさり)
するものあれば、腰に長き棹を挟、もしあやまちて落入ときは、竿にて死を遁るゝといへり。
さて又一面に氷あれども、根本温泉の地ゆへ、しかも氷薄し。氷簿きゆへ、氷をうがちて漁(
すなどり)する也。其薄氷の上人馬不危往来することを、ふしんして、奇とすべし。
もし氷のあるうち、此湖水へ沈没(ちんもつ)する人あれば、畚(ふご)に鶏を入て、氷のうへを
ひくに、其鶏のなく所の下、はたして尸(しかばね)をうるといふ。是亦妙也。
然るに遠山のうち、秋葉の奥の院かつ坂を下りて、北の方の渓間(たにま)に、凡二丈四方な
る盤石(ばんじゃく)あり。畳を舗たるごとくにて、苔むしたりしが、奇妙なる岩なり。
大人小児にかぎらず、いづくともなく迷ひてしれざるを、尋ぬるあたりなければ、此所に来り、
供物を捧げ、一時精進して、身清浄にして、めぐり合せ下さるべしと、信をこめてねがひ、鶏
一羽携来て、其盤石のうへに置ば、迷ふ人の方角へ、鶏あゆみて鳴。
又鳴ざる所は其方角にて死したりとしる。道の遠近も、鶏のあゆむにて知るべきよし。
しかはあれど、願人すこしにても嘲る心底あれば、鶏も歩ことをせずと也。
これは諏訪とは、事は違へども、様子の霊なることは、同じこと也。
第十四章へ
補注へ